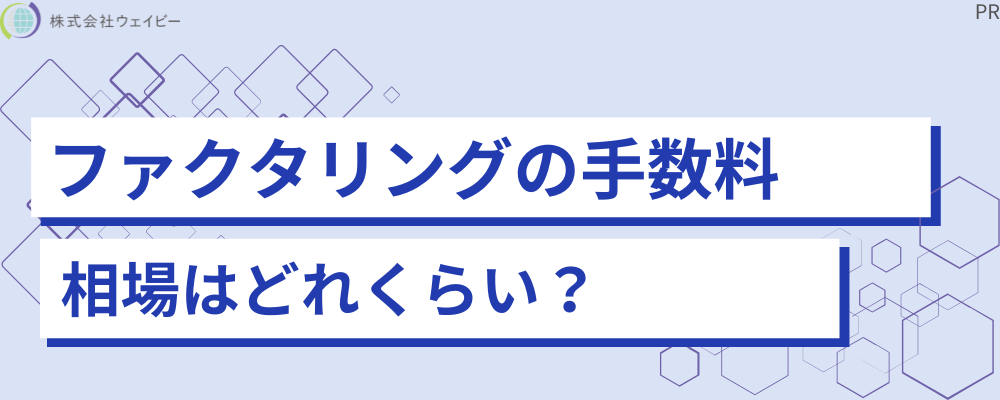ファクタリングの手数料相場は、下記の通りです。
- 2社間ファクタリング:8%〜18%
- 3社間ファクタリング:2%〜9%
ただし、手数料以外にも、債権譲渡登記費用や印紙代などの諸費用がかかる場合があります。
また、ファクタリングの手数料は、売掛先の信用力や売掛金の金額など、さまざまな要因で変動します。
少しでも費用を抑えるためには、複数のファクタリング会社から見積もりを取り、比較検討することが大切です。
そこで本記事では、ファクタリングの手数料相場だけでなく、手数料以外にかかる諸費用や手数料を抑える方法についても解説します。
合わせて、おすすめのファクタリング会社についても紹介します。
ファクタリングの手数料について詳しく知りたい方や、ファクタリングの利用を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
ファクタリングで手数料以外にかかる諸費用
ファクタリングでは、手数料以外にもいくつかの諸費用が発生する場合があります。
これらの費用は、ファクタリング会社や契約内容によって異なりますが、事前に把握しておくことで、予期せぬ出費を防げます。
ファクタリング利用にかかる主な諸費用としては、下記の通りです。
| 費用項目 | 金額目安 | 概要・備考 |
|---|---|---|
| 債権譲渡登記費用 | 1件あたり7,500円 | 法務局で債権譲渡を登記する際に発生第三者対抗要件を満たすために必要な法定費用 |
| 印紙代 | 通常200円 | 書面契約時に印紙税法に基づいて課税される電子契約の場合は非課税(印紙代不要) |
| 事務手数料 | 数千円〜1万円程度 | 審査や資料取得などの事務処理に伴う手数料会社によっては手数料込み、もしくは無料の場合もある |
| その他の費用 (出張費や交通費など) | 数千円〜数万円程度 | 担当者の訪問対応時に発生遠方や交通手段によって金額が変動無料対応の会社もある |
次項で、それぞれの諸費用について詳しく解説します。
債権譲渡登記費用
債権譲渡登記費用とは、売掛金などの債権を第三者(ファクタリング会社など)に譲渡したことを、法務局に登記する際にかかる費用のことです。
登記手続きの申請手数料は、1件あたり7,500円と定められています。
この費用は、下記のような目的で設定されています。
- 登記を行うことで「第三者対抗要件」を満たし、債権譲渡が法的に有効となる
- 登記情報を公示・閲覧可能な状態に保つためのインフラ維持費
- 法務局の運営や人件費を支える財源として
債権譲渡登記を行うことで、債権の二重譲渡などのトラブルを防止し、取引の安全性を確保できます。
印紙代
印紙代とは、債権譲渡契約書を紙の書面で取り交わす場合に発生する税金(印紙税)のことです。
これは印紙税法に基づく法定費用であり、契約金額に応じて課税されます。
ファクタリング契約のように、金銭の受け渡しに関する内容を含む契約書は「課税文書」に該当し、1万円以上の契約には通常200円の印紙税が必要です。
印紙税を納めることで、契約書の法的効力を高め、取引の安全性を確保する役割があります。
とはいえ、近年では、電子契約サービスを使ったオンラインファクタリングが増加しています。
電子契約で締結された契約書は紙の文書ではないため、印紙税の課税対象外となり、印紙代は不要です。
そのため、コストを少しでも抑えたい方は、オンラインファクタリングも検討してみましょう。
事務手数料
事務手数料とは、ファクタリング契約に伴い、ファクタリング会社が書類作成や各種手続きにかかる実務コストとして請求する料金のことです。
この費用には、下記のような業務に関連するコストが含まれる場合があります。
- 審査にかかる作業費用
- 登記簿謄本などの資料取得費用
- 書類郵送・交通費・事務処理に伴う雑費
一般的に、事務手数料は数千円〜1万円程度で設定されるケースが多く、固定額で提示される場合と、契約金額に応じて変動する場合があります。
なお、すべてのファクタリング会社が事務手数料を徴収しているわけではなく、手数料に含まれている場合もあります。
事務手数料の金額や取り扱いはファクタリング会社によって異なるため、契約前に見積書や契約書で確認することが大切です。
「手数料が安いと思ったら、事務手数料が別で発生した」というケースもあるため、費用の内訳は必ずチェックしましょう。
その他の費用(出張費や交通費など)
ファクタリング会社によっては、担当者が利用企業を訪問して契約の説明や書類の受け渡しを行うケースがあります。
その際、出張費や交通費などの実費が別途請求される場合があります。
費用の目安としては、一般的には数千円程度ですが、遠方への出張や新幹線・飛行機などの高額な交通手段を利用する場合は、数万円程度かかるケースもあるでしょう。
ただし、ファクタリング会社によっては、これらの費用を事務手数料に含めていたり、無料にしていたりする場合もあります。
そのため、事前に出張費や交通費の有無について確認しておきましょう。
2社間ファクタリングの手数料・諸費用相場
2社間ファクタリングの手数料相場は、8%〜18%程度です。
手数料は、売掛先の信用力や売掛金の金額、入金期日までの期間などによって変動します。
2社間ファクタリングは、売掛先を介さずにファクタリング会社と利用者の間で契約を行うため、売掛先にファクタリングの利用を知られたくない場合におすすめです。
しかし、3社間ファクタリングと比較すると、手数料は高めに設定されています。
さらに、2社間ファクタリングでは、手数料のほかに下記のような諸費用がかかる場合があります。
| 費用項目 | 内容・備考 |
|---|---|
| 債権譲渡登記費用 | 債権譲渡登記が求められた場合に、登録免許税として1件あたり7,500円が発生必要に応じて司法書士報酬も追加 |
| 印紙代 | 書面契約時に発生通常は200円程度電子契約の場合は非課税(印紙代不要) |
| 事務手数料 | 数千円〜1万円程度書類作成や審査関連の処理に伴う費用会社によっては手数料込み、もしくは無料の場合もある |
| 出張費・交通費など | 担当者の訪問対応時に発生遠方や交通手段によって金額が変動無料対応の会社もある |
これらの諸費用をすべて含めたトータルコストは、数万円程度になることが一般的です。
2社間ファクタリングは、売掛先(取引先)にファクタリングの利用を知られにくいというメリットがある一方で、コスト面ではやや割高になる傾向があります。
そのため、手数料だけでなく諸費用も含めた総額を見積もったうえで、利用の検討をしましょう。
3社間ファクタリングの手数料・諸費用相場
3社間ファクタリングの手数料相場は、2%〜9%程度です。
手数料は、2社間ファクタリングと同様に、売掛先の信用力や売掛金の金額、入金期日までの期間などによって変動します。
3社間ファクタリングは、売掛先を含めた3社間で契約を行うため、2社間ファクタリングよりも手数料が安く設定されています。
ただし、3社間ファクタリングにおいても、手数料のほかに下記のような諸費用がかかる場合があります。
| 費用項目 | 内容・備考 |
|---|---|
| 印紙代 | 書面契約時に発生通常は200円程度電子契約の場合は非課税(印紙代不要) |
| 事務手数料 | 数千円〜1万円程度書類作成や審査関連の処理に伴う費用会社によっては手数料込み、もしくは無料の場合もある |
これらの諸費用をすべて含めたトータルコストは、数千円〜数万円程度です。
3社間ファクタリングでは、基本的に債権譲渡登記は不要のため、2社間ファクタリングよりも総費用を抑えやすい傾向があります。
とはいえ、3社間ファクタリングは、手数料と諸費用を抑えやすい反面、売掛先の協力が必要になるという特徴があります。
そのため、手数料と諸費用を含めたトータルコストだけでなく、事業状況や取引先との関係性を踏まえたうえで、利用の検討をしましょう。
ファクタリングの手数料が決まる要因
ファクタリングの手数料が決まる要因は、下記の通りです。
- 売掛先の信用力
- 売掛金の金額
- 請求書の入金までの期限
- ファクタリングの利用歴
- 契約形態(2社間・3社間)
これらの要因を理解することで、手数料を抑え、より有利な条件でファクタリングを利用できます。
次項で、それぞれの手数料が決まる要因について詳しく解説します。
売掛先の信用力
ファクタリングの手数料は、主に「売掛金を回収できる可能性」をもとに決定されます。
この中でも特に重要なのが、売掛先の信用力です。
売掛先の信用力が低い場合、期日通りに売掛金が支払われないリスクが高まるため、ファクタリング会社はその分のリスクを加味して、手数料を高めに設定する傾向があります。
例えば、下記のようなケースでは、信用リスクが高いと判断されやすくなります。
- 売掛先の財務内容が不安定
- 業績が悪化している
- 業界全体に景気変動の影響を受けやすい
一方で、大企業や安定した業種の売掛先は、支払い能力に信頼性があると評価されやすく、手数料が低く設定される場合が多いです。
例えば、下記のようなケースでは、信用リスクが低いと判断されやすくなります。
- 上場企業や長年の取引実績がある法人
- 公共機関やインフラ系などの安定業種
- 経営が黒字かつ自己資本比率が高い企業
ファクタリングを利用する際は、「自社の信用力」だけでなく、「売掛先の信用力」が手数料に大きく影響することを理解しておきましょう。
特に、2社間ファクタリングの場合は、売掛先の情報をより詳細に提供することで、手数料の引き下げに繋がる可能性もあります。
売掛金の金額
売掛金の金額も、ファクタリングの手数料を決定する要因の1つです。
ファクタリング会社にとって、高額な売掛債権を扱う場合、少額の債権を多数扱うよりも効率的に利益を上げられます。
例えば、100万円の売掛債権1件を処理するのと、10万円の売掛債権10件を処理するのでは、後者の方が手間と時間がかかります。
また、売掛金の金額が大きくなっても、事務処理にかかるコストが金額に比例して増加するわけではありません。
そのため、ファクタリング会社は高額な売掛債権に対して、低い手数料率で対応しても利益を確保しやすくなります。
ただし、売掛金の金額が大きくても、売掛先の信用力が低い場合はリスクが高まるため、手数料は高く設定される可能性があります。
手数料を左右する最大の要素は、あくまでも「売掛先の信用力」であることを理解しておきましょう。
請求書の入金までの期限
ファクタリングの手数料は、請求書の入金までの期限(支払いサイト)によっても変動します。
入金までの期限が長いほど、その間に売掛先の経営状況が悪化したり、倒産したりするリスクが高まります。
つまり、ファクタリング会社にとって、入金までの期限が長い売掛債権は、回収不能になるリスクが高いということです。
そのため、ファクタリング会社は、入金までの期限が長い売掛債権に対しては、リスクを考慮して手数料を高く設定します。
例えば、支払いサイトが30日以内の場合、比較的リスクが低く、手数料は低め(2〜5%程度)に設定されやすい傾向があります。
一方で、支払いサイトが90日以上の場合、経済状況や売掛先の変動リスクが増すため、手数料が高め(10%以上)になるケースもあるでしょう。
ファクタリングの利用歴
ファクタリングの手数料は、売掛先の信用力や売掛金の内容だけでなく、利用者自身のファクタリング利用歴にも左右されます。
過去に問題なくファクタリングを利用し、期日通りに売掛金を支払った実績があれば、ファクタリング会社からの信用度が高まります。
信用度が高い利用者は、売掛金の回収リスクが低いと判断されるため、手数料が低く設定されるケースが多いです。
また、同じファクタリング会社を継続的に利用している場合は、手数料の割引や審査の簡素化など、取引条件が優遇される可能性もあるでしょう。
一方で、過去に売掛金の支払い遅延やトラブルがあった場合、ファクタリング会社からの信用度は低下します。
信用度が低い利用者は、売掛金の回収リスクが高いと判断されるため、手数料が高く設定されたり、利用を断られたりする可能性があります。
特に、2社間ファクタリングの場合、売掛金の回収を利用企業に委ねるため、利用者の信用度がより重要視される点を覚えておきましょう。
契約形態(2社間・3社間)
ファクタリングの手数料は、契約形態(2社間・3社間)によっても変動します。
これは、ファクタリング会社が負うリスクの大きさが異なるためです。
2社間ファクタリングは、ファクタリング会社と利用企業の2者間で契約を結び、売掛先には契約内容を通知せずに資金調達を行うため、下記のようなリスクを負います。
- 利用企業が売掛金を回収できないリスク
- 売掛先が支払いを拒否・遅延する可能性
こうしたリスクの高さを反映し、2社間ファクタリングの手数料は高め(8〜18%程度)に設定される傾向があります。
一方で、3社間ファクタリングは、売掛先を含めた3者間で契約を交わし、売掛金の支払いが直接ファクタリング会社に行われるため、下記のようにリスクを軽減できます。
- 売掛先から確実に回収できる前提で契約できる
- 利用企業を介さないため、資金回収の確度が高い
そのため、手数料は比較的低く(2〜9%程度)設定される傾向があります。
ノンバンクファクタリングより銀行系ファクタリングの方が手数料は低い傾向にある
銀行系ファクタリングは、ノンバンクファクタリングに比べて手数料が低い傾向があります。
手数料が低くなる主な理由は、下記の通りです。
- 資金調達コストが低い
- 信用力が高く、低金利で運営可能
- 信用評価のノウハウが豊富
銀行は、顧客から預金を集めることで安価に資金を調達できるため、ノンバンクに比べて運用原資のコストが低く抑えられます。
また、銀行は金融庁の監督下にあり、社会的信用度も高いため、外部からも低金利で資金を調達できる仕組みがあります。
そのため、銀行はファクタリング手数料を低く設定することが可能です。
さらに、融資業務で培った与信ノウハウや、独自の信用情報ネットワークにより、売掛先の信用力を的確に分析・評価できる点も、過剰な手数料を設定せずに済む要因の1つです。
ただし、銀行系ファクタリングは手数料が安い反面、下記のような制約もあるため注意しましょう。
- 審査が厳しく、時間がかかる
- 利用できる売掛債権に金額や業種の制限がある
- オンラインで完結しない場合が多い
下記に、銀行系ファクタリングとノンバンク系ファクタリングの特徴を簡単にまとめました。
| 銀行系ファクタリング | ノンバンク系ファクタリング | |
|---|---|---|
| 手数料 | 比較的低い | やや高めの傾向 |
| 審査 | 厳しく時間がかかる傾向 | 柔軟かつスピーディー |
| 利用条件 | 売掛先・金額に制限あり | 小口・個人事業主でも利用できる |
銀行系はコスト面で魅力的ですが、スピードや柔軟性を重視する場合はノンバンク系との比較検討がおすすめです。
ノンバンクでもオンライン完結のファクタリング会社なら手数料を抑えられる
ノンバンク系ファクタリングは一般的に銀行系より手数料が高めですが、オンライン完結型のファクタリング会社を選べば、手数料を抑えられる可能性があります。
手数料が抑えられる主な理由は、下記の通りです。
- 運営コストが大幅に削減されている
- 書類提出や審査の自動化による効率化
- 新興企業が多く、手数料競争が起こりやすい
オンライン完結型では、店舗運営費や人件費がかからないため、従来の対面型よりも運営コストを大幅に削減できます。
また、書類提出や本人確認を含むプロセスをWeb化・AI化することで、審査スピードが早く、人的リソースの削減にも繋がります。
さらに、オンライン完結型のファクタリング会社は、比較的新しいサービスのため、競争が激しく、手数料の引き下げが起こりやすいとも言えるでしょう。
ただし、手数料の安さだけで判断するのではなく、下記のような点も合わせて確認しましょう。
- 手数料に追加費用(事務手数料・登記費用など)が含まれているか
- 契約条件に債権譲渡登記や償還請求権の有無があるか
- サポート体制やセキュリティ対応が信頼できるか
下記に、オンライン完結型のファクタリングを利用するメリット・デメリットを簡単にまとめました。
| メリット | デメリット |
| 時間と場所を選ばないスピーディーな資金調達ができる(最短即日入金)対面不要でプライバシーが守られる | 2社間ファクタリングしか利用できない必要書類をデータ化しないといけない対面とは違い柔軟な対応が難しい |
オンライン完結型は、手数料を抑えつつスピーディーな資金調達が可能ですが、サービスの信頼性や条件も含めて総合的に判断することが大切です。
法的にはファクタリングの手数料に上限はないので業者選びには注意が必要
ファクタリングは融資ではなく「債権の売買」にあたるため、利息制限法や出資法などのように手数料の上限を定めた法律がありません。
そのため、手数料は業者ごとの自由設定となっており、中には悪質な業者が法外な手数料や不当な費用を請求するケースもあります。
特に注意が必要なのは、下記のような業者です。
- 闇金に近い実態を持つ業者(表向きはファクタリング)
- 初回提示の手数料が極端に安すぎる業者
これらの業者は、法外な手数料や、脅迫的な取り立てを行う場合があります。
また、後から高額な手数料を上乗せしたり、契約内容に不利な条件を盛り込んだりする可能性もあります。
万が一、悪質なファクタリング会社と契約してしまった場合は、消費者センターや弁護士、警察などに早めに相談しましょう。
放置すると、トラブルが拡大する恐れがあります。
悪徳業者を見抜くポイントは下記の通りです。
- 手数料が相場より著しく高い、または低い
- 契約内容が不透明
- 会社の情報が公開されていない
- 口コミや評判が極端に悪い
- 担当者の対応が高圧的・説明が曖昧
これらのポイントに注意し、「安い」「即日入金可能」といった甘い言葉だけに惑わされず、信頼できるファクタリング会社を選びましょう。
ファクタリングの手数料に関するよくある質問
ここでは、ファクタリングの手数料についてよくある質問をまとめました。
ファクタリングの利用を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
ファクタリング手数料の消費税の扱いは?
ファクタリング手数料の消費税の扱いは、債権譲渡登記の有無で異なります。
- 債権譲渡登記がある場合:消費税の課税対象
- 債権譲渡登記がない場合:消費税の課税対象外
ただし、上記はあくまで原則であり、個別の契約内容によって異なる場合があります。
例えば、債権譲渡登記がない場合でも、契約内容次第で「資金提供」と見なされることがあり、貸付に該当すれば非課税です。
もし不安な場合は、ファクタリング会社や税理士に確認してみましょう。
ファクタリング手数料の計算方法は?
ファクタリング手数料は、下記の計算式で求められます。
- 手数料 = 売掛金金額 × 手数料率
例えば、100万円の売掛金で手数料率が10%の場合、手数料は10万円です。
実際に受け取れる金額は、下記の計算式で求めます。
- 受取金額 = 売掛金金額 – 手数料
上記の例では、実際に受け取れる金額は90万円です。
ただし、上記はあくまで一般的な計算方法であり、ファクタリング会社によって異なる場合があります。
事務手数料や印紙代、登記費用などの別途費用が加算されるケースもあるため、総費用として確認することが大切です。
ファクタリング手数料の会計処理は?
ファクタリング手数料は、原則として「売上債権売却損」として処理します。
これは、売掛債権を売却することで発生した損失とみなされるためです。
ただし、使用している会計ソフトに「売上債権売却損」の勘定科目がない場合は、「支払手数料」や「雑損失」などの勘定科目で処理するケースもあります。
例えば、2社間ファクタリングを利用して売掛金100万円をファクタリングし、手数料10万円が差し引かれて90万円が入金された場合の仕訳例は、下記の通りです。
| 借方 | 貸方 | ||
| 普通預金 | 900,000円 | 売掛金 | 1,000,000円 |
| 売上債権売却損 | 100,000円 | ||
3社間ファクタリングの場合は、基本的な仕訳は2社間ファクタリングと同じですが、売掛先からの入金確認など、3社間特有の仕訳が発生するケースがあります。
会計処理について不明な点があれば、税理士や会計士などの専門家に相談するのがおすすめです。
ファクタリングの手数料はいつ支払う?
ファクタリングの手数料の支払いタイミングは、2社間ファクタリングと3社間ファクタリングで異なります。
2社間ファクタリングの場合は、売掛先からの入金後、速やかにファクタリング会社へ支払う必要があります。
支払い期日は、売掛金の入金日当日、または入金日から数日以内に設定されるケースが多いです。
そのため、売掛金の入金と同時に、ファクタリング会社への支払い準備をしておきましょう。
一方で、3社間ファクタリングの場合は、売掛先からファクタリング会社へ直接入金されるため、利用企業が手数料を支払う必要はありません。
ただし、契約内容によっては、手数料以外の費用(債権譲渡登記費用など)の支払いが必要なケースがあります。
ファクタリング会社が高額な手数料を請求しても違法にならない理由は?
ファクタリングは、売掛債権の「売買契約」であり、貸金業法で規制される「融資」とは異なります。
そのため、貸金業法で定められた上限金利(利息制限法)の適用を受けません。
ファクタリングと融資の具体的な違いは、下記の通りです。
| 融資(貸付) | 借入金に対して利息が発生し、「利息制限法」や「出資法」により上限金利が規定される |
| ファクタリング | 売掛債権を売却することで資金化する取引であり、「債権譲渡契約」にあたるため、金利規制の適用外 |
つまり、ファクタリングは「利息」ではなく「手数料」として費用が発生する仕組みであり、その料率に上限を設ける法律がありません。
また、契約は、当事者間の自由な意思に基づいて成立するという「契約自由の原則」があります。
ファクタリング契約も、この原則に基づいて成立するため、当事者間で合意した手数料であれば、基本的に有効となります。
これらの理由により、ファクタリング会社は、法律上の上限金利に縛られずに手数料を設定することが可能です。
ただし、法的には問題がなくても、手数料が相場(一般的には2〜20%程度)から大きく外れている場合は、刑事罰や行政処分の対象となるケースもあります。
これを避けるために、悪質業者は名目を変えて費用を追加請求するケースもあるため、手数料だけでなく、契約内容全体を確認し、信頼できるファクタリング会社を選びましょう。
まとめ
ファクタリングは、売掛債権を売却して早期に資金化できる便利な資金調達手段です。
ただし、手数料や諸費用(登記費用・印紙代・事務手数料など)がかかるため、事前に総額を確認することが大切です。
なお、手数料は、売掛先の信用力や契約形態、売掛金額によって変動します。
ファクタリングの手数料を抑えるためには、複数のファクタリング会社から見積もりを取り、比較検討することが大切です。
また、オンライン完結型のファクタリング会社を利用すれば、手数料を抑えられる可能性があります。
ファクタリングを活用する際は、手数料や諸費用、契約内容などを十分に理解したうえで、信頼できる会社を選びましょう。