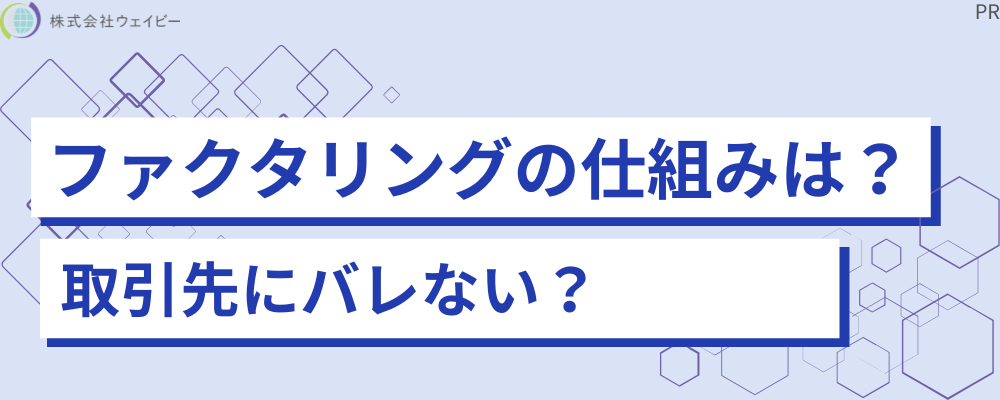ファクタリングとは、企業が保有する売掛債権をファクタリング会社に売却することで、売掛金の支払期日前に現金化できる資金調達方法です。
売掛金の現金化により、企業の資金繰り改善だけでなく、ビジネスチャンスの拡大に繋げられるでしょう。
銀行融資とは異なり、担保や保証人なしで利用できる可能性もあります。
しかし、ファクタリングにはさまざまな種類があります。
2社間や3社間といった取引形態によっても仕組みや特徴が異なるため、どのサービスを選ぶべきか迷っている方もいるでしょう。
そこで本記事では、ファクタリングの仕組みや種類、メリット・デメリット、利用時の注意点などを網羅的に解説します。
ファクタリングとは
ファクタリングとは、企業が保有する売掛債権をファクタリング会社に売却し、期日前に現金化する資金調達方法です。
売掛金は将来入金される予定の売上ですが、期日(入金日)までには時間がかかります。
しかし、ファクタリングを利用すれば、売掛金を早期に現金化し、資金繰りを改善することが可能です。
近年、政府も中小企業の資金調達手段の多様化を推進しており、ファクタリングは選択肢の1つとして注目されています。
ファクタリングを政府が推奨している理由
政府がファクタリングを推奨する理由は、中小企業の資金繰り改善と経営安定化に貢献するためです。
具体的には、売掛金を早期に現金化することで、中小企業は資金繰りの悪化を防ぎ、経営の安定化を図れます。
また、担保や保証人に依存しない資金調達手段として、金融機関からの融資が難しい企業でも利用しやすいのが特徴です。
さらに、売掛先の倒産リスクを軽減し、連鎖倒産を防ぐ効果も期待されています。
これらの点から、ファクタリングは中小企業にとって有効な資金調達手段として、政府から推奨されています。
下請債権保全支援事業について
下請債権保全支援事業とは、中小企業庁が実施する、下請企業の売掛債権の保全と資金化を支援する施策です。
具体的には、信用保証協会と連携し、ファクタリング会社が下請企業の売掛債権を買い取りやすくするための施策です。
また、手数料の一部を国が補助することで、中小企業の負担軽減を図っています。
さらに、地域金融機関や商工会議所と連携し、ファクタリングの普及と相談体制の整備も行っています。
下請債権保全支援事業によって、特に大企業との取引で長い支払いサイトを強いられている中小企業は、資金繰りの改善と連鎖倒産リスクの軽減が可能です。
手形や小切手は廃止・縮小の方針について
政府は、中小企業の取引適正化を目指し、2026年までに約束手形の利用廃止を目指す方針を示しました。
この背景には、手形取引が中小企業の資金繰りを圧迫している現状があります。
手形取引の縮小に伴い、金融庁や中小企業庁は、電子記録債権(でんさい)と並び、売掛金を早期に現金化できるファクタリングを代替手段として推奨しています。
手形取引の廃止による中小企業への影響を軽減するため、今後も政府は下請債権保全支援事業などを通じて、ファクタリング利用企業への支援を拡充していくでしょう。
ファクタリングの種類
ファクタリングには、主に下記の5つの種類があります。
- 売掛債権を売却する「買取型ファクタリング」
- 売掛先の支払い保証に特化した「保証型ファクタリング」
- 複数の債権をまとめて扱う「一括ファクタリング」
- 医療機関向けの「医療ファクタリング」
- 海外取引に特化した「国際ファクタリング」
それぞれの特徴を理解し、自社のニーズに合ったファクタリングを選ぶことが重要です。
次項で、それぞれのファクタリングについて詳しく解説します。
買取型ファクタリング
買取型ファクタリングとは、売掛債権をファクタリング会社に売却し、所有権を移転する方式です。
売掛先の支払い不能リスクはファクタリング会社が負担するため、利用企業はリスクを回避できます。
会計上は売掛金の売却として処理され、財務指標の改善にも繋がります。
そのため、売掛先の信用リスクを移転したい中小企業や、バランスシートを改善したい企業におすすめです。
ただし、手数料は高めで、売掛先との関係に影響を与える可能性がある点に注意が必要です。
保証型ファクタリング
保証型ファクタリングとは、売掛債権の所有権は利用企業に残したまま、ファクタリング会社が支払いを保証する方式です。
売掛先の支払い不能時には、ファクタリング会社が代位弁済を行います。
そのため、売掛金の回収リスクを軽減したい企業や、信用リスク対策を重視する企業におすすめです。
ただし、買取型に比べて手数料は低いですが、バランスシート改善効果は限定的です。
また、売掛金の管理は引き続き自社で行う必要がある点には注意しましょう。
一括ファクタリング
一括ファクタリングとは、複数の売掛債権をまとめて買い取る方式です。
継続的な取引がある売掛先との債権を対象とし、事前に契約した枠内で随時資金化できます。
事務負担とコストを削減できるため、特定の取引先と安定的な取引がある中小企業や、事務処理の効率化を図りたい企業におすすめです。
ただし、契約期間中は特定のファクタリング会社との取引に固定される点や、売掛先が限定される点に注意が必要です。
医療ファクタリング
医療ファクタリングは、医療機関が保有する診療報酬債権を対象としたサービスです。
診療報酬は、保険者からの支払いが法律で保証されているため、一般的な売掛債権に比べてリスクが低いという特徴があります。
診療報酬の入金にはタイムラグがありますが、医療ファクタリングを利用すれば、早期の資金化が可能です。
そのため、開業初期の医療機関や、設備投資を計画している医療機関におすすめです。
ただし、診療報酬の減額査定リスクや、将来的な制度変更リスクを考慮する必要があります。
国際ファクタリング
国際ファクタリングは、輸出入取引における売掛債権を対象としたサービスです。
為替リスクや国家リスクなど、国際取引特有のリスクをカバーし、海外取引における資金繰りの安定化を支援します。
そのため、海外に輸出を行う中小製造業者や、新興国市場への参入を図る企業におすすめです。
ただし、手数料は国内ファクタリングに比べて高額になる傾向があり、国や地域によってサービス内容や条件が異なる点に注意が必要です。
ファクタリングを取り扱っている会社
ファクタリングサービスは、銀行や独立系ファクタリング会社など、さまざまな企業によって提供されています。
それぞれの特徴を理解し、自社のニーズに合った会社を選ぶことが重要です。
次項で、それぞれの企業で取り扱っているファクタリングについて詳しく解説します。
銀行
銀行が提供するファクタリングサービスは、その信用力と安定性が最大の強みです。
銀行またはその子会社がサービスを提供するため、利用者にとっても信頼性が高く、安心して取引できます。
審査は厳格で、売掛先の信用力や企業の財務状況が重視されますが、通過すれば比較的低い手数料で利用できることが多いです。
また、融資や預金など、他の銀行サービスと組み合わせて利用できるため、総合的な資金調達が可能です。
ただし、審査に時間がかかる場合や、小口取引に対応していない場合がある点、また、銀行内部の規定や金融規制により柔軟性に欠ける場合がある点に注意しましょう。
独立系
独立系ファクタリング会社は、銀行系に比べて審査が柔軟で、迅速な対応が期待できます。
独自の審査基準を持ち、売掛先の信用力を重視するため、財務状況に課題がある企業でも利用しやすいと言えるでしょう。
また、小口案件や短期の取引にも対応できるため、幅広いニーズに応えられます。
企業の個別事情に合わせたカスタマイズも可能で、柔軟なサービス提供にも期待できます。
ただし、手数料は銀行系に比べて高めに設定されることが多く、悪質な業者も存在するため、会社選びは慎重に行う必要があるでしょう。
2社間ファクタリングと3社間ファクタリングの概要と流れ
ファクタリングは、主に2社間ファクタリングと3社間ファクタリングの2つ取引形態があります。
それぞれにメリット・デメリットがあり、自社の状況やニーズに合わせて適切な形態を選択することが重要です。
次項で、それぞれの契約形態について詳しく解説します。
2社間ファクタリング
2社間ファクタリングは、利用企業とファクタリング会社の2社間で取引が完結する形態です。
売掛先企業に債権譲渡の通知を行わないため、取引先に知られることなく資金調達が可能です。
売掛金の回収は利用企業が行い、回収後にファクタリング会社へ支払います。
手数料は3社間ファクタリングより高めですが、審査から資金化までのスピードが速いのが特徴です。
そのため、取引先に知られたくない場合や、迅速な資金調達を希望する場合におすすめです。
ただし、二重払いリスクや、利用企業の信用リスクが高い点に注意しましょう。
2社間ファクタリングを利用する際の流れは、下記の通りです。
- 利用企業がファクタリング会社に売掛債権の買取を申し込む
- ファクタリング会社が売掛債権と利用企業の審査を行う
- 審査通過後、売買契約を締結する
- ファクタリング会社が利用企業に資金を入金する
- 売掛先企業は通常通り利用企業に売掛金を支払う
- 利用企業は回収した資金をファクタリング会社に支払う
- 支払い完了により取引が終了する
上記の流れで、売掛先企業に知られることなく、迅速な資金調達が行えます。
3社間ファクタリング
3社間ファクタリングは、利用企業、ファクタリング会社、売掛先企業の3者間で行われる取引形態です。
売掛先企業に債権譲渡通知を行い、売掛金は売掛先からファクタリング会社へ直接支払われます。
手数料は2社間ファクタリングより低いですが、売掛先に知られる点がデメリットです。
そのため、手数料を抑えたい場合や、売掛金の回収業務を委託したい場合におすすめです。
ただし、売掛先の承諾が必要な点や、今後の取引に影響を与える可能性がある点に注意しましょう。
3社間ファクタリングを利用する際の流れは、下記の通りです。
- 利用企業がファクタリング会社に売掛債権の買取を申し込む
- ファクタリング会社が売掛債権と売掛先企業の審査を行う
- 審査通過後、売買契約を締結する
- 売掛先企業に対して債権譲渡通知を行う
- ファクタリング会社が利用企業に資金を入金する
- 売掛先企業はファクタリング会社に直接支払いを行う
- 入金確認により取引が完了する
上記の流れで、売掛金の回収リスクを軽減し、安定した資金繰りを行えます。
ファクタリングの償還請求権とは?
ファクタリングの償還請求権とは、売掛先が支払い不能になった際、ファクタリング会社が利用企業へ支払いを求める権利です。
償還請求権の有無によって、下記の3種類に分かれます。
| 種類 | 詳細 |
|---|---|
| リコース(償還請求権あり) | 売掛先が支払えない場合、利用企業が代わりに支払う必要があり、融資に近い性質を持つ |
| ノンリコース(償還請求権なし) | 売掛先が支払えなくても利用企業の支払いは不要で、売掛先の信用リスクはファクタリング会社が負担する |
| 一部リコース | 特定の条件でのみ償還請求権が発生する契約形態 |
リコース型の注意点として、最終的な支払い責任は利用企業にあるため、売掛先の信用力調査が重要です。
また、契約書で償還請求権の条件を詳細に確認し、会計処理上の扱いも理解しておく必要があります。
銀行系は基本リコース型
銀行系ファクタリングは、基本的にリコース型(償還請求権あり)です。
これは、銀行のビジネスモデルが低リスク・低リターンを基本としているため、安定した収益を確保できるリコース型が好まれるからです。
また、銀行にとってファクタリングは融資の代替手段としての側面が強く、既存の与信管理体制や審査基準を活用しやすいというメリットもあります。
しかし、リコース型には注意点もあります。
売掛先が支払えなかった場合、手数料を支払った上に売掛金全額の返済義務も生じるため、コスト負担が大きくなる点です。
また、融資に近い形態のため、契約期間中に財務制限条項が設けられるなど、経営の自由度が制限される可能性もあります。
ノンバンクは基本ノンリコース型
ノンバンク系ファクタリングは、基本的にノンリコース型(償還請求権なし)です。
これは、ノンバンクがリスクテイクを前提としたビジネスモデルを採用しており、高いリスクを取ることで高い手数料を設定できるからです。
また、銀行系との差別化を図り、売掛先の信用リスクを完全に引き受けることで競争力を高めています。
さらに、柔軟な審査基準と価格設定が可能であり、専門的な債権回収ノウハウを活用することで、高リスク案件でも引き受けられるからとも言えるでしょう。
ただし、ノンリコース型にも注意点があります。
リスクを完全に引き受けるため、手数料が銀行系より高くなる傾向があります。
他にも、特定条件下では償還請求権が発生する例外規定が設けられている場合があるため、契約条件や例外規定を詳細に確認するようにしましょう。
ファクタリングを利用するメリット
ファクタリングは、売掛金を売却することで早期に資金調達できるサービスです。
担保や保証人が不要で、信用情報にも影響を与えにくいというメリットもあります。
次項で、それぞれのメリットについて詳しく解説します。
すぐに資金調達できる
ファクタリングを利用する最大のメリットは、売掛金の回収を待たずに即座に資金化できることです。
通常2〜3ヶ月かかる売掛金の入金を、最短即日で現金化できます。
銀行融資のような長い審査期間もなく、多くのファクタリング会社では数時間から数日で資金調達が可能です。
また、ファクタリングの審査では、売掛先の信用力が重視されるため、自社の財務状況が芳しくない場合でも、優良企業との取引があれば資金調達できる可能性が高いです。
これにより、急な資金需要や事業拡大のチャンスにも柔軟に対応できます。
ただし、迅速な資金調達には手数料がかかる点に注意が必要です。
特に即日資金化を希望する場合は、通常よりも高い手数料が設定されることがあります。
他にも、急いで契約すると契約内容の確認が不十分になり、不利な条件を見落とすリスクもあります。
ファクタリングはあくまで短期的な資金繰り改善策であり、長期的な経営課題の解決にはならない点も理解しておきましょう。
担保や保証人が不要
ファクタリングでは、売掛債権そのものが商品として買い取られるため、不動産や機械設備などの担保や、経営者の個人保証は原則不要です。
通常の融資とは異なり、企業の資産価値ではなく、売掛先の支払能力が評価の対象となります。
担保設定の手続きや費用も不要で、既存の担保余力に関係なく資金調達が可能です。
そのため、担保提供可能な資産がない場合や、すでに融資で担保を設定している場合でも、売掛債権があれば資金調達の選択肢が広がります。
ただし、ファクタリングの手数料は担保・保証人付き融資よりも高くなる傾向があります。
また、リコース型(償還請求権あり)のファクタリングでは、実質的に経営者保証を求められるケースもあるため注意が必要です。
売掛先の信用力が低い場合や、個人事業主との取引では審査に通らないこともあります。
信用情報に影響しない
ファクタリングは、銀行融資とは異なり、借入ではなく債権売却の形態を取るため、信用情報機関に「融資」として記録されません。
そのため、将来的な借入枠にも影響を与えません。
また、買取型(ノンリコース型)のファクタリングの場合、会計処理上は負債として計上されないため、バランスシートにも影響を与えないのもメリットです。
銀行の融資審査でも、借入総額の算定対象外となるのが一般的です。
ただし、リコース型(償還請求権あり)の場合は、会計処理上負債として計上される可能性があり、信用評価に影響を与えることがあります。
さらに、ファクタリングの利用が過剰になると、金融機関から経営が不安定であると判断される可能性もあるため注意しましょう。
ファクタリングを利用するデメリット・注意点
ファクタリングは便利な資金調達手段ですが、手数料の高さや取引先に知られるリスクなど、注意すべき点もいくつかあります。
次項で、ファクタリングを利用するデメリット・注意点について詳しく解説します。
手数料がかかる・高い
ファクタリングは、銀行融資と比較して資金調達コストが高額になる傾向があります。
一般的なファクタリングの手数料率は1%〜10%程度であり、銀行融資の金利(1%〜3%程度)と比較すると高コストです。
手数料の計算方法も複雑で、基本手数料、事務手数料、審査料など複数の費用が設定されている場合、総支払額が当初の想定を超えることもあります。
また、支払いサイト(期間)が長いほど手数料率が上昇する傾向があり、90日以上の長期の売掛債権では特に高率となる点にも注意が必要です。
ファクタリングを頻繁に利用すると、高コストの負担が積み重なり、より資金繰りを悪化させる可能性があります。
そのため、契約書の手数料条件を細部まで確認し、総コストを正確に把握することが大切です。
取引先にバレる可能性がある
3社間ファクタリングでは、法的に債権譲渡通知が必要なため、売掛先企業に、ファクタリングを利用している事実が知られます。
そのため、特に保守的な大企業の場合、資金繰りに困窮しているという印象を与え、取引条件の見直しや取引停止を検討されるリスクがあります。
取引先に知られたくない場合は、2社間ファクタリングを利用しましょう。
2社間ファクタリングは、債権譲渡通知を行わないため、取引先に知られることなく資金調達が可能です。
調達できる資金に上限がある
ファクタリングで調達できる資金は、売掛債権の金額が上限となります。
売掛金額の100%を調達することはできず、手数料を差し引いた金額(通常は債権額の80%〜95%程度)が実際に調達できる上限です。
また、ファクタリング会社ごとに買取可能な上限額が設定されており、特に中小規模の会社では大口の債権を1度に買い取れない場合があります。
そのため、調達可能な上限額を事前に確認し、必要資金を確保できるかどうかを慎重に検討しましょう。
単一の会社では上限に達する場合でも、複数社を併用すれば必要資金を確保できる可能性があります。
個人事業主・フリーランスもファクタリングを利用できる
ファクタリングは、企業だけでなく個人事業主やフリーランスも利用可能です。
ファクタリングには、個人事業主・フリーランス向けのファクタリングサービスがあり、少額から利用できる点や、柔軟な審査基準が特徴です。
ただし、手数料や審査基準など、注意するべき点もあります。
次項で、個人事業主・フリーランスもファクタリングを利用できる理由や注意点などを詳しく解説します。
個人事業主・フリーランス向けのファクタリングがある
個人事業主やフリーランス向けのファクタリングは、企業に対する請負業務や納品した商品・サービスの対価として発生した売掛債権を買取対象としています。
法人向けに比べて取引金額が小さい場合が多いため、数万円からの小口債権にも対応しているサービスが多いです。
ただし、個人事業主は法人と比較してリスクが高いと判断される場合が多く、その分手数料率が高く設定されるのが一般的です。
また、売掛先の審査基準も厳格になるケースが多いです。
特に売掛先が個人や小規模事業者の場合は、信用力不足と判断されて審査に通らないケースや、高い手数料率が適用されることがあるでしょう。
個人事業主特化であれば少額から利用できる
個人事業主特化型のファクタリングは、数万円からの小口債権に対応している点が特徴です。
一般的な法人向けファクタリングの最低利用額が100万円前後であるのに対し、個人事業主特化型では5万円〜10万円程度からの少額債権でも買取対象となる場合が多いです。
個人事業主特化型のファクタリング会社が少額から利用できる背景には、少額取引に適した審査プロセスを採用している点が挙げられます。
具体的には、申込書類の削減や審査手続きの効率化によって、少額取引でも採算が取れるビジネスモデルとなっています。
ただし、手数料の実質負担率が高くなる点には注意しましょう。
少額取引では固定費部分の影響で実質手数料率が高くなりやすく、例えば5万円の債権で5,000円の手数料が発生すると10%もの負担となります。
また、少額から気軽に利用できる反面、頻繁な利用は資金繰りを悪化させ、事業収益を圧迫する恐れもあります。
ファクタリング利用で審査されるポイント
ファクタリングの審査では、売掛金の内容、売掛先の信用力、支払いサイト、取引実績、契約内容、そして利用者の過去の利用歴などが総合的に評価されます。
次項で、それぞれのポイントについて、なぜ審査で重要視されるのか、具体的な審査内容などを詳しく解説します。
売掛金の内容
ファクタリング会社は、リスクの評価や手数料設定のために、審査の際に売掛金の内容を重視しています。
具体的には、売掛先の信用力が高く、満期までの日数が短い売掛金ほど審査が有利です。
また、売掛先とファクタリング利用会社との間に複数回継続的な取引実績があることも重要です。
売掛先の信用力
ファクタリング審査では、利用企業の信用力ではなく売掛先の信用力が審査対象になります。
具体的には、売掛先の財務状況や支払い能力、過去の支払い履歴、業界での評判などを総合的に評価します。
業績が安定している大手企業や上場企業は、信用力が高いと判断されやすく、審査が有利です。
また、過去に支払い遅延や未払いがないかどうかも重要な判断材料となります。
支払いサイト(期間)の長さ
支払いサイト(期間)の長さも審査の重要なポイントで、一般的に、支払いサイトが短いほど審査が有利です。
90日以内の支払いサイトは比較的審査が通りやすいですが、120日や180日など長期になるとリスクが高いと判断されます。
また、業界標準と比較して著しく長い支払いサイトは、取引の健全性に疑問を持たれる可能性があります。
支払いサイトの長さは、手数料率にも影響し、長期になるほど手数料が高くなる傾向がある点にも注意しましょう。
売掛先との取引実績
売掛先との取引実績は、ファクタリング審査において信頼性を評価するための重要なポイントです。
具体的には、継続的な取引期間、取引量と頻度、過去の支払い実績などが評価されます。
長期間にわたって安定した取引がある場合や、取引量が多く定期的な取引がある場合は、信頼性が高いと判断されるでしょう。
また、正式な契約書、注文書、納品書、請求書などの書類が整っていることも、取引の信頼性を示すうえで重要なポイントです。
売掛先との契約内容
売掛先との契約内容も審査の重要なポイントです。
特に、債権譲渡禁止特約の有無は最重要項目であり、契約書にこの特約がある場合はファクタリングが利用できない可能性があります。
また、契約の解除条件や支払い条件、相殺条項、検収条件、瑕疵担保責任の範囲なども審査対象です。
売掛先との契約内容は、債権回収のリスクを評価するために審査されます。
契約内容が不明瞭であったり、リスクが高いと判断された場合は、審査に通らない可能性があります。
利用者が過去に同社でのファクタリング利用歴があるか
利用者が過去に同一のファクタリング会社で利用歴がある場合、その取引実績と返済履歴が重視されます。
過去に問題なく取引を完了している場合は、審査においてプラス要因となります。
また、ファクタリングの利用頻度や金額の推移、手続きの正確性なども評価対象です。
過去にトラブルがあった場合は、その内容や解決状況も含めて総合的に判断されます。
ファクタリングを装った悪徳業者に注意
ファクタリングは資金調達の方法として便利な手段ですが、悪徳業者が存在することも事実です。
高額な手数料や不明瞭な契約条件、違法な行為など、悪徳業者の手口は多岐にわたります。
悪徳業者に騙されないためには、特徴や見分け方を事前に理解し、慎重にサービスを選ぶ必要があります。
次項で、悪徳業者の特徴と悪徳業者を見抜くポイントについて詳しく解説するので、ぜひ参考にしてください。
悪徳業者の特徴
悪徳業者は、異常に高額な手数料を要求するのが特徴です。
一般的なファクタリングの手数料率は1%〜10%程度ですが、20%〜30%以上の高額な手数料を設定している場合は注意しましょう。
また、契約前に「事務手数料」「審査料」などの名目で前払い金を要求する業者も避けるべきです。
通常、債権買取前の段階で料金を請求することはほとんどありません。
他にも、契約書の内容が不明瞭であったり、重要事項の説明が不十分だったりする業者にも注意が必要です。
特に小さな文字で書かれた不利な条件や、口頭での説明と契約書の内容が異なる場合は危険です。
悪徳業者を見抜くポイント
悪徳業者を見抜くためには、まず手数料の透明性と妥当性を確認することが重要です。
総額で何%の手数料がかかるのか明示されない場合や、業界平均(1%〜10%程度)を大幅に上回る手数料を提示される場合は警戒すべきです。
また、契約書の内容を詳細に確認し、不明瞭な表現や理解しづらい条件が含まれていないか確認しましょう。
特に違約金や追加費用に関する条項は注意が必要です。
登録状況や事業実態の調査も重要です。
金融庁・財務局の貸金業者登録や第二種金融商品取引業の登録有無を確認し、実際のオフィスの有無や事業年数、法人登記情報などで実態を把握しましょう。
これらのポイントを意識しながら、実際の口コミや評判も確認することで、悪徳業者との取引を回避できます。
ファクタリングでよくある質問
ファクタリングでよくある質問は、下記の通りです。
- でんさいファクタリングとは?
- ファクタリングと融資は違う?
- 給料ファクタリングとは?
- ファクタリング会社への支払いが遅れたらどうなる?
- ファクタリングの支払い方法は?
次項で、それぞれの質問について回答していきます。
でんさいファクタリングとは?
でんさいファクタリングとは、電子記録債権(でんさい)を活用したファクタリングサービスです。
従来の紙ベースの手形や売掛金とは異なり、電子化された債権を対象としています。
でんさいネット上で電子的に記録・管理される債権を活用するため、紛失や盗難のリスクがなく、印紙税も不要です。
また、支払期日前の資金化や債権の分割が可能であり、企業の資金繰り改善に期待できます。
政府の推進する手形の電子化政策と連動しており、手形取引からの移行を進める企業にとっておすすめの資金調達手段です。
ファクタリングと融資は違う?
ファクタリングと融資は、資金調達の手段として異なります。
ファクタリングは売掛債権の「売却(譲渡)」であり、売掛金をファクタリング会社に売却して資金を得ます。
一方、融資は金融機関からの「貸付」であり、将来的に元本と利息の返済が必要です。
会計上、ファクタリングは資産の入れ替えであり、融資は負債の増加です。
審査では、ファクタリングは売掛先の信用力が重視され、融資は利用企業の信用力が重視されます。
また、ファクタリングは原則として返済義務がありませんが、融資は返済義務があります。
給料ファクタリングとは?
給料ファクタリングとは、従業員が将来受け取る予定の給与(未払い給与)を、ファクタリング業者に買い取ってもらうことで、給与日前に現金を得るサービスです。
しかし、一般的なファクタリングと異なり、多くの問題点があります。
例えば、未払い給与を買い取る形式のため、高額な手数料が設定されているケースが多いです。
また、給料ファクタリングは、名目上は債権の売買ですが、実質的には金銭の貸付と変わらないため、貸金業法の規制対象となる可能性があります。
他にも、高金利による債務の膨張リスクや、貸金業法違反の可能性、生活困窮時の利用による経済的困難など、労働基準法上の問題点もあります。
そのため、給料ファクタリングはリスクが高いため、資金繰りに困った場合は、まず金融機関からの融資や、公的支援制度の利用を検討しましょう
ファクタリング会社への支払いが遅れたらどうなる?
ファクタリング会社への支払いが遅れた場合、ファクタリングの種類によって影響が異なります。
2社間ファクタリングの場合、遅延損害金が発生し、督促や法的手続きが取られる可能性があります。
また、今後のファクタリング利用が制限されたり、信用情報機関に延滞情報が登録される可能性もあるでしょう。
一方、3社間ファクタリングの場合、主に売掛先企業の支払い遅延が問題となり、ファクタリング会社から売掛先企業への督促が行われます。
保証型の場合は、最終的に利用企業に支払い義務が戻る可能性があります。
ファクタリングの支払い方法は?
2社間ファクタリングの場合、利用企業が売掛先から回収した資金をファクタリング会社の指定口座に銀行振込で支払います。
一方、3社間ファクタリングの場合、売掛先企業がファクタリング会社に直接支払います。
債権譲渡通知により支払先が変更されるため、利用企業側での支払い手続きは不要です。
いずれの場合も、契約書に記載された支払期日を厳守する必要があります。
支払期日を過ぎた場合、遅延損害金が発生する可能性があります。
なお、支払い方法や条件は、各ファクタリング会社によって異なるため、契約時に詳細を確認しておきましょう。
ファクタリングをうまく活用すれば資金繰りを改善できる
本記事では、近年注目されている資金調達方法のファクタリングについて解説しました。
ファクタリングは、売掛債権を売却することで資金調達を行うサービスであり、企業の資金繰りを改善するための便利な手段です。
自社の信用状況が悪くても利用できる可能性があるため、資金調達の選択肢の1つとして検討する価値があります。
しかし、「手数料が高い」「調達できる資金に上限がある」など、注意すべき点もいくつかあります。
ファクタリング業者を装った悪徳業者も忘れてはいけません。
本記事で解説したファクタリングの仕組み、種類、メリット・デメリット、注意点などを参考に、自社の資金繰り状況に合わせて信頼できるファクタリング会社を選びましょう。
ファクタリングは、適切な知識と注意を持って利用すれば、企業の成長を力強くサポートしてくれるでしょう。