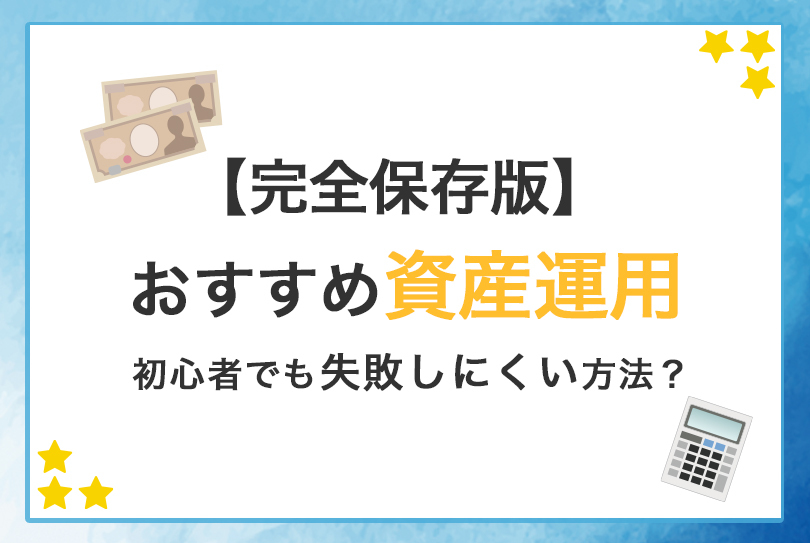低金利が続く昨今では、銀行にお金を預けていてもほとんど増えません。公的年金制度の変化によって、老後の生活資金に不安を感じている人も多いです。子供の教育費や住宅購入資金など、将来のために少しでも蓄えを増やしておきましょう。
本記事では、効率的にお金を増やす手段として、おすすめの資金運用を9つご紹介します。資産運用をしたことがない初心者の方でも失敗しにくい方法や、投資先のメリット・デメリットなどを詳しくお伝えします。
記事の後半では、少額から投資できるネット証券や元手1,000万円でできる投資情報も載せていますので、ぜひ参考にしてください。
今すぐおすすめランキングが見たい方は、下のボタンを押してください。
資産運用とは?
資産運用とは、自分の資金を株式や不動産などに投資、運用して資産を増やすことです。運用方法には、銀行口座の預貯金から、投資の代名詞的な株式や仮想通貨などさまざまな方法があります。
中にはハイリスク・ハイリターンなものもあるため、資産運用に対してギャンブルのようなイメージを持つ人もいるでしょう。しかし、ローリスクで始められて手堅く運用できるものも少なくありません。多くの企業が資産運用サービスを提供しているので、それぞれの特徴を掴んで自分にあったものを選んでみましょう。
ただし、投資すると必ずリターンが得られてお金が増えるとは限らない点に要注意です。場合によっては、マイナスとなって損をする可能性もあります。こうしたリスクを把握した上で、資産運用を実際にスタートする前に知識を学ぶことが重要です。
資産運用の種類【ローリスクローリターン】
おすすめのローリスク・ローリターンの資産運用方法を5つ紹介します。比較的リスクを抑えられる運用方法であるため「これから資産運用を始めていきたい」「まずは資産運用に慣れてみたい」という方向きです。しかし、リスクがゼロというわけではないという点には注意が必要です。
- 外貨預金
- 債券(国債・社債)
- 預金
- 金投資
- アンティークコイン
それでは、ひとつずつ詳しく紹介していきます。
①外貨預金|為替レートの変動を利用した投資
外貨預金とは、海外の通貨を銀行口座に預けておく運用方法です。為替レートは日々変わっているため、その変動差額を利用してお金を増やします。預け入れ時点よりも外貨の価値が高くなった(円安)タイミングで日本円に交換すると、リターンが大きくなる仕組みです。
外貨預金は、日本の銀行口座で始められることに加え、オンライン上でも操作ができます。また、日本の銀行よりも金利が比較的高い海外の口座に預金するという方法も有効です。ただ、利益を得るためには、為替相場やレートをこまめにチェックする必要があるでしょう。日本で円を預金するのとではレートの変動幅や仕組みなどが大きく異なる場合もあるので、どの通貨を運用するのかしっかりと見定めましょう。
| メリット | ・為替レートによっては大きなリターンも期待できる ・預け入れした後は基本何もしなくていい |
| デメリット | ・短期的なリターンは期待できない ・為替相場や為替レートを頻繁にチェックする必要がある |
②債券(国債・社債)|購入後は待つだけのローリスク・ローリターンな投資
債券は、国や企業などが発行する有価証券のことで、投資家からの資金調達を目的として発行されます。国が発行する国債や企業が発行する社債を購入すると、半年に一度利息が支払われます。個人向け国債は、額面金額1万円からと手軽に始められ、最低年0.05%(税引前)の金利元本が保証されています。
元本が投資家に戻ってくる償還日が決められており、満期になると額面に記されている金額が返ってきます。一度購入すれば、償還日まで持っているだけで定期的にリターンが得られる点がメリットとして挙げられます。また、国債の場合は国が責任を持ってサポートしているため、安全性が高くリスクは少ないでしょう。他にも代表的な債券として、地方債や外国債などの名前が挙げられます。それぞれの特性を理解した上で運用を始めることをおすすめします。
| メリット | ・購入して償還日まで待つだけでいい ・国債は国が管理しているため安全性が高く低リスク |
| デメリット | ・社債の場合、発行元の倒産リスクがある ・途中売却すると、価格の変動により価値が下がる可能性もある |
③預金|誰でも簡単にできるがリターンは少ない

預金は、銀行口座にお金を預けておいて、金利でお金を増やしていく方法です。銀行など預け先が倒産しない限り元本は確保されます。口座に入金する以外はやることもないので、安全性が高く安心して続けられる方法です。
ただ、金利がわずかであり、大きなリターンを得ることが難しい点はデメリットといえます。例えば、三菱UFJ銀行は「普通預金」の金利を年0.001%(変動金利)にて設定しています。資産運用によってお金を増やしていきたいという方には少々物足りないかもしれません。
| メリット | ・預け元が倒産しない限り元本は確保される ・預けた後は何もしなくていい |
| デメリット | ・金利がごくわずか ・長期的に運用しても増額はさほど見込めない |
④金投資|価値は世界共通。盗難に注意
名前のとおり、お金をゴールドの現物に換えておく方法です。金は世界共通の価値で取引されており、価値が保証されているためローリスクな投資先といえます。株式や不動産などに投資している人の分散投資としてもおすすめです。1800年代から金投資は行われており、歴史的にも安定した投資方法の一つです。
為替同様に、金の価格は日々変動しています。タイミング次第ではリターンが狙えますが、逆に損してしまう可能性もある点に注意しましょう。また、基本的には自己管理になるため、盗難対策が必要です。金投資には「金地金」や「純金積立」などの様々な方法があります。自分に合った金投資のやり方を探すことをおすすめします。
| メリット | ・世界共通の価値がある ・価格がゼロになることはない |
| デメリット | ・金価格の変動によって損する可能性がある ・盗難リスクがある |
⑤アンティークコイン|年々価値が高まるコレクションとしても魅力的な投資
アンティークコインは、昔使われていたお金(硬貨)のことで、近年注目を集める投資先のひとつです。今後生産されることはないため、数が限定されており、経年とともに希少価値は高まります。世界中にコレクターが存在しており、時間とともに高い値段で取引できる可能性もあるでしょう。
紀元前後に使われていた「古代コイン」や中世に発行されていたコイン、高い彫金技術で美しい肖像をモチーフとしている「近代コイン・近代銭」などの種類があります。コインの価値は発行された年数とグレードによって変わります。
金貨一枚は数万円から販売されていますが、オークションでは億を超えるものも扱われています。金投資と同様に、現物を管理する際には盗難対策が必須です。また、偽物の流通量も多いため、知識や経験が豊富な信頼できるディーラーの元で購入しましょう。
| メリット | ・価値が下がる可能性はほとんどない ・購入して保管しておくだけで価格が上がる |
| デメリット | ・盗難などのリスク管理 ・偽物に注意が必要 |
資産運用の種類【ミドルリスクミドルリターン】

ミドルリスクミドルリターンが見込める資産運用方法を紹介します。株式投資や投資信託、不動産投資などは元々人気でしたが、iDeco(個人型確定拠出年金)などの個人年金も最近はスポットを浴びているようです。
- 株式
- 不動産
- 投資信託
- つみたてNISA/NISA
- iDeCo
- ソーシャルレンディング
- ETF投資
- REIT投資
- 外貨MMF
- ロボアドバイザー
それぞれの特徴やメリット・デメリットについてもお伝えしますので、参考にしてください。
①株式|成功すれば大きな利益が得られるがリスクは高め
企業が自社の資金調達のために発行する株式に対して投資する方法です。株式を取得するとその企業の株主となり、配当金として利益が還元されます。また、株式優待という形で自社製品や限定サービスの提供を受けるケースも少なくありません。
食品メーカーであれば自社の開発製品を提供、飲食店であればお食事券を提供といった具合です。株式投資では、豊富な銘柄から自由に選択でき、場合によっては大きなリターンも期待できるでしょう。ただ、100株単位での購入が基本となり、初期費用が必要です。
| メリット | ・資金や目的によって銘柄を自由に選択して投資できる ・成功すれば大幅なリターンが得られる可能性も |
| デメリット | ・基本的に100株単位での購入となるため初期費用が高額になる ・損失が大きくなる可能性があり、投資知識を必要とする |
なお、「【裏ワザ?】初心者におすすめの株式投資のコツや始め方を徹底解説 | アプリや勉強方法もご紹介」では、初心者におすすめの株式投資について詳しく解説しています。株式投資で資産運用を検討中の方は、ぜひご覧ください。
LINE証券はスマホアプリに特化したネット証券サービスで、国内株式を1株から購入できる手軽さが魅力です。低価格帯の銘柄も多数扱っていることに加え、チャートがシンプルでわかりやすいので、ぜひ下記からLINE証券に申し込んでみてください。
②不動産|長期的な運用で資産を作る。自然災害などのリスクに注意が必要
不動産投資は、マンションやアパートなどの物件を購入して賃料収入や売却益を得る方法です。初心者には難しく感じるかもしれませんが、ローンを利用すれば少ない資金でも運用可能です。
短期で利益を得るのではなく、長期的な運用で大きな資産形成を目指します。物件の管理や入居者とのトラブルなどが心配な場合は、業務管理を専門業者に委託可能です。一方で、空室の発生や家賃の下落、自然災害などのリスクを考慮しておく必要があります。
| メリット | ・ローンを利用すれば少ない資産で大きな収益が期待できる ・面倒な物件の管理は専門業者に委託できる |
| デメリット | ・空室の発生や家賃の下落、自然災害などで減収になるリスクがある ・土地や建物の価値が下落する恐れがある |
JPリターンズは、不動産初心者が確かな知識を持って投資に進むことをサポートするため、投資セミナーを実施しています。1部をマンション投資セミナー、2部を個別の質疑応答・相談にあてており、内容も非常に充実。スムーズな投資への理解を助けているので、ぜひ下記からJPリターンズの不動産投資セミナーに申し込んでみてください。
③投資信託|分散投資でリスクを軽減。手数料を忘れずに
投資信託では、運用のプロであるファンドマネージャーが投資家からお金を集めて、投資・運用します。ファンドマネージャーが利益を得た場合に配当金を受け取れるため、資金運用の時間が取れない人にも最適の運用方法です。
金融商品は価格が変動するため、元本保証はなく、手数料も発生します。銀行の預金とは違い、確実に利益を得られるわけではないという点には充分に注意を向けておきましょう。しかし、株や債権、不動産など複数の投資先に分散投資を行うことでリスクを緩和できます。少額から始められる商品も多数登場しており、初心者から上級者まで幅広い層におすすめです。
| メリット | ・投資のプロに運用を委託でき、初心者にもおすすめ ・少額の資金で始められ、リスクの分散も可能 |
| デメリット | ・ファンドマネージャーに投資を依頼する際に手数料がかかる ・元本保証がないため、多額の損失が発生する可能性も |
なお、「【2021年最新】投資信託のおすすめ人気ランキング5選 | メリット・デメリットも解説 」では、投資信託について詳しく解説しています。投資信託による資産運用を検討している方は、こちらも併せてご覧ください。
④つみたてNISA/NISA|個人投資家向けの税制優遇制度

NISAとは、個人投資家向けの税制優遇制度のことで、投資信託や株などの資産運用で得た利益が一定額まで非課税となります。NISA専用口座で投資・運用を行った場合が対象で、新規投資額で毎年120万円が上限です。各年に購入した金融商品を保有している間に得た配当金や、値上がりした後に売却して得た利益は、購入から5年間は課税されません。非課税となる投資総額は最大600万円です。
通常のNISA以外にも、つみたてNISAやジュニアNISAなどの種類があります。つみたてNISAは月々1,000円からと少額積立が可能。最長20年、年間40万円の非課税投資枠があります。信託報酬は安めですが、手数料が無料の商品のみを使っており、長期運用に最適です。対象は「口座を開設する年の1月1日時点で日本在住の20歳以上の人」となっています。
iDeCoと違い、掛け金は所得控除の対象となりませんが、投資資金はいつでも引き出せます。投資額や期間によって非課税額が異なる点にも注意しましょう。
| メリット | ・配当金や売却益が非課税で、利益が出やすい ・月1,000円前後と少額から運用可能 |
| デメリット | ・1人1口座のみ開設できる ・新規での投資限定である |
Wealth navi|「長期・積立・分散」をサポートする資産運用サービス

引用元:Wealth navi公式HP
WealthNaviは、「長期・積立・分散」といった3つの資産運用を全自動で行ってくれるサービスです。世界約50カ国11,000の銘柄に自動で分散投資を行うため、中長期的に利益を狙っていけるシステムとなっています。高度な知識も必要ないため、手軽に投資を進めていきたいユーザーにおすすめです。
| 手数料 | 預かり資産の年率1%(税込1.1%) |
| 最低投資額 | 10万円 |
⑤iDeCo|個人で作る年金。掛け金が所得控除できる
iDeCoは、老後のために個人で積み立てる年金です。自分で拠出した掛け金を保険や投資信託などの金融商品で運用し、原則60歳以降に年金や一時金として受け取ります。iDeCoの掛け金は全額所得控除の対象で、運用益も非課税となり、退職時の税金負担も優遇される設定です。
さらに、一時金や年金として受け取る場合、一定額まで税金がかかりません。積立金額はすべて「所得控除」の対象となっており、所得税や住民税の節税に効果的です。運用で得た利益も非課税となります。2017年以降は、公務員や主婦も加入できるようになりました。原則60歳まで引き出せない点だけはデメリットですが、公的年金だけでは不安な人におすすめです。
| メリット | ・ほとんどの人が加入でき、老後の生活費を個人で積み立てられる ・所得税や住民税などの税金対策になる |
| デメリット | ・基本的に60歳まで引き出せない ・運用方法によっては元本割れの可能性がある |
iDeCoについては「【令和3年最新】初心者におすすめの資産運用ランキング5選|少額から始めてみよう!」でも触れています。興味のある方や詳しく知りたい方は、こちらも読んでみてください。
⑥ソーシャルレンディング|満期まで待つだけのラクラク投資で利回りも高い。投資先の見極めが重要

ソーシャルレンディングとは、お金を借りたい人や企業と投資家や投資企業を結びつけるネット上の融資仲介サービスです。融資を受けたい企業に対して、個人投資家などが出資する融資型クラウドファンディングの一種でもあります。ソーシャルレンディングは、貸主と借主のニーズ双方を満たしたマーケットとして近年注目を集めつつあります。資金調達の一手段として検討をしてみていいでしょう。マーケット型、オークション型、貸付型・ファンド型などの種類があります。
平均5〜10%と高い利回りで運用される点が、最大のメリットです。また、元本の価格変動がなく、投資した後は満期になるまで手を付ける必要がありません。1万円からの投資も可能です。ただ、借り手が返済不能になった場合、元本が返ってこない可能性が出てきます。
| メリット | ・利回りが5〜10%ほどと高い ・満期償還まで待つだけ |
| デメリット | ・短期的に大きなリターンは期待できない ・借り手のデフォルトにより元本が全額または一部返済されない可能性がある |
⑦ETF投資|指数連動・分散投資でリスクを抑える
ETF(Exchange Traded Fund)投資とは、日経平均株価やNYダウなどの指数と連動するように運用されている投資信託のことです。証券会社の口座を通じて、株式と同じように売買できます。ETFの仕組み上、ひとつの銘柄に投資すると自動的に分散投資されるため、リスクを抑えた投資が可能です。ETFは、取引所が開いている間はリアルタイムで取引が可能となっています。この点も株式投資と同じ点です。
値動きがわかりやすく、通常の投資信託よりも保有コストが安く済むため、長期投資の選択肢としてもおすすめでます。ただ、市場の需給によっては投資信託の基準価額と市場価格が乖離してしまう可能性がある点に注意が必要です。
| メリット | ・ひとつの銘柄に投資すると自動的に分散投資されリスクを抑えられる ・値動きがわかりやすい |
| デメリット | ・投資信託の基準価額と市場価格が乖離する可能性がある ・分配金の再投資は手動で行わなければならない |
⑧REIT投資|不動産特化型投資信託
REIT(Real Estate Investment Trust)とは、不動産に特化した投資信託のことです。投資会社が多くの投資家から資金を集めて、複数の不動産に投資して運用、その利益を得ることができます。一般的な不動産投資には高額の資金が必要ですが、数万円程度から投資できる銘柄も少なくありません。また、投資会社が運用の実務を行うため、管理の手間もほとんどかかりません。手間はかからない一方で、不動産の稼働状況などはしっかり確認することが可能です。不動産の種類は、商業施設やマンション、オフィスビルなど多岐にわたります。
「不動産投資は魅力的だけど初期費用が高いから」とあきらめていた方にもおすすめです。ただ、元本が保証されていないため、金融市況や不動産市況の影響で価格や利益が大きく変動する可能性があります。また、株式のような配当控除が利用できない点にも注意しましょう。
| メリット | ・少額から不動産投資ができる ・運用のプロに任せられる |
| デメリット | ・元本保証がないため価格や収益が変動する ・配当控除の対象ではない |
⑨外貨MMF|複利運用が期待できる投資方法。日本円との交換の際の手数料に注意

外貨MMF(Money Market Fund)とは、外貨で運用される投資信託です。米ドル建て商品が代表的ですが、比較的安全性の高い優良企業の社債や、国債などに投資されます。1万円の少額から取引ができ、積立にも対応。運用利益は再投資が可能なので、複利効果も期待できるでしょう。運用実績に応じた分配が日々行われ、月ごとの分配金は月末にまとめて元本に再投資されます。
売買手数料は無料ですが、外貨と日本円を交換する際に為替手数料が発生し、保有期間中には信託報酬が発生します。また、発行元の財務状況などによっては、現地通貨ベースで価格が変動する可能性がある点にも注意が必要です。
| メリット | ・優良企業の社債や国債などに投資されるため比較的安全性が高い ・運用利益は再投資が可能で、複利効果も期待できる |
| デメリット | ・外貨と日本円を交換する際に為替手数料がかかる ・保有期間中には信託報酬がかかる |
⑩ロボアドバイザー|運用はAIにおまかせ。投資初心者におすすめの投資方法
ロボアドバイザーとは、投資家の代わりにAIが投資先や金融商品を選んでくれるサービスです。資産状況やリスク、年齢などに応じた客観的な視点から取引ができるため、資産運用の知識が浅い初心者に適した投資方法といえるでしょう。国内外の株式や債券、金、不動産など、いくつかの資産をバランスよく組み合わせながら投資を進めてくれるシステムです。
しかし、AIのアドバイス通りに投資したとしても、元本割れをしてしまうリスクはあります。過信せずに知識や情報を用いて適切な判断を下す訓練をすることも大切です。
| メリット | ・投資の知識不要で気軽に始められる ・客観的な判断で投資ができる |
| デメリット | ・元本割れの可能性がある ・手数料がかかる場合がある |
資産運用の種類【ハイリスクハイリターン】
投資経験者や上級者向けの、短期間で大きなリターンも狙えるハイリスク・ハイリターンの資産運用方法もあります。主に下記の3種類がおすすめです。
- 先物取引
- FX
- 仮想通貨
それぞれについて詳しく見ていきましょう。
①先物取引|知識と経験が豊富な人向け
先物取引とは、将来の価値をあらかじめ予測して、売却価格や取引日を決めた上で金融商品や石油などを購入する方法です。平均的なリターンは5〜15%とされています。相場が上昇すると予想される際には「買い」から、相場が下落すると予想される際には「売り」から取引をスタートすることが基本です。
価値が必ず上がるであろう商品に限定して投資したとしても、未来は変わる可能性があります。もし予測が外れ、取引時期に商品の価値が下がっていた場合、大損となるでしょう。それでも、必ず取引をしなければなりません。投資経験が豊富で、知識や情報を駆使できる人に向いている運用方法といえます。
| メリット | ・購入時点で将来的な取引が決定できる ・平均的に5〜15%のリターンが得られている |
| デメリット | ・商品の価値が下がっていたても取引しなければならないため損する ・的確に予測することが難しいハイレベルな投資方法 |
②FX|レバレッジで自己資金より大きな投資が可能。失敗した場合の損失の大きさに注意
FXは、外国為替証拠金取引のことで、日本と外国の為替変動により収益を得るものです。よく知られた投資方法ですが、高いリターンが望める一方、失敗すると大きな損失を生む可能性があるハイリスクな資産運用となっています。非常にリスクが高く、かなりの経験を必要とする資産運用方法なので、会社によっては「デモトレード」の機能を用意しています。
24時間取引が可能なため、早く収益を得たい人には魅力的です。しかし、定期的に値動きチェックしてこまめに売買するなど、専門的な知識が必要です。初心者はある程度勉強してから参入することをおすすめします。
| メリット | ・うまくいけばレバレッジ効果で大幅なリターンが期待できる ・少額から始められ、早く収益に繋げられる |
| デメリット | ・短期間で資産の大部分を失う可能性がある ・世界情勢をはじめとする専門知識が必要 |
なお、「【2021年最新】FX口座のおすすめ比較ランキング9選|初心者からプロまでジャンル別におすすめをご紹介 」では、FXについて詳しく解説しています。FXで資産運用を検討中の方は、ぜひご覧ください。
③仮想通貨|平均利回りは高いが値動きが激しい。税金も高め
ビットコインなどの仮想通貨も資産運用方法のひとつです。インターネット上に存在する仮想の通貨を取引して、利益を得ます。近年のトレンドでもあり、購入時の手数料も比較的安価で始めやすくなっています。仮想通貨取引所での購入や、マイニングと呼ばれる手段によって仮想通貨は入手可能です。
平均利回りは約10〜20%ですが、値動きが激しく、不確実性が高い点はデメリットです。価格が跳ね上がった場合、いわゆる億り人になる可能性もありますが、逆に暴落した場合は資産を大きく失うでしょう。また、税金が高い点も注意が必要です。仮想通貨の運用にあたっては、充分な知識を得てから取り組むといいでしょう。
| メリット | ・オンライン上で手軽に購入できる ・購入時の手数料は安め |
| デメリット | ・価格変動が大きく不安定 ・他の運用方法に比べて税金が高い |
資産運用のメリット

資産運用には主に次の3つのメリットがあります。それぞれのメリットを適切に理解し、計画的に資産運用を始めましょう。
- 資産を増やせる
- 不労所得が得られる
- 経済・税金の知識が身につく
一般的にメリットとして捉えられている資産増加の他にも、多くの利点が資産運用にはあります。それぞれの項目について詳しく解説していきます。
資産を増やせる
資産運用そのものによって資産を増やすだけでなく、運用方法によっては複利効果も狙うことが可能です。複利効果とは、元本だけでなく利息にも利息が上乗せされて資金が増える仕組みです。単利は元本にのみしか利息がつきませんが、複利は利息が利息を呼ぶために長期的な資産運用において大きな効果を発揮します。
普通預金の金利が年0.001%とすると、100万円を預けても1年間で10円の利息しかつきません。
しかし、年利5%で100万円を運用した場合1年で105万円となり、さらにその1年後には110.25万円になるのです。複利効果によって、資産を効率よく増やせます。
不労所得が得られる
自らが働いて得る所得ではなく、家賃収入や配当金などの「働かなくても得られる収入」を不労所得といいます。不労所得は資金運用を始めてすぐに得られるわけではなく、ある程度の元手となる資金が必要です。資産運用で資産を増やせれば、その資産を元手として安定した不労所得を得られる可能性があります。
具体的な不労所得の例としては「不動産投資による家賃収入」「株式保有による配当金」「預貯金により発生する利子」などが挙げられます。
経済・税金の知識が身につく
資産運用を始めると、自然と経済や税金などの知識を身につけることができます。株式や外貨は世界経済と連動しているため、投資している商品や為替相場などをチェックしながら経済などを学ぶことが可能です。
なお、一定の利益が出た場合は会社員でも確定申告が必要になり、税金の知識も得られるでしょう。資産運用を通して身についた知識は一生モノであり、自身の仕事や家族の生活も役立ちます。資産運用を続けていくことによって、有益な幅広い知識を学ぶことができるでしょう。
資産運用のデメリット

一方で、資産運用によるデメリットもあります。代表的なものとしては、次の2点です。
- 元本割れの可能性がある
- 時間と知識が必要
ひとつずつ詳しく見ていきましょう。
元本割れの可能性がある
投資で資産運用をする場合、元本割れをする可能性があります。元本割れとは、運用している資産の価格が下がることによってその価値が元本を下回ってしまうことを指す言葉です。収益(リターン)の裏には必ずリスクがあるということを覚えておきましょう。
資産運用を行うことで必ずお金が増えるわけではありません。元本割れを100%防ぐ方法はありませんが、分散投資や長期的な運用方法を選ぶことで、リスクを緩和することはできます。元本割れしない金融商品もありますが、安全性が高い反面大きな利益を得ることは難しいという点には注意が必要です。
時間と知識が必要
資金運用は、短期的な取引で収益を得るわけではないので、資産が成長するまである程度の時間がかかります。また、資産運用の手段に応じて金融や経済、不動産などの専門知識が必要になるため、勉強を続けていくことが必要です。
年々新たな形の資産運用が世に出続けています。それに伴い、その知識を常に学び続けていくことが資産運用においては求められるでしょう。日々時間をかけて知識を増やし、情報をアップデートしていくことが資産運用を進めていく上では非常に大切です。古い知識のみで資産運用を進めていくのは、大きなリスクを伴うということを覚えておきましょう。
このようなメリット・デメリットを理解した上で、資産運用の方法を考えましょう。
資産運用で初心者が失敗しないための注意点
資産運用で初心者が失敗しないためには、以下の4つの点に注意が必要です。
- 収益のシミュレーションをしておく
- 本などを読んで勉強しておく
- 長期で複利のメリットを活かす
- 少額で始める
それぞれ詳しく見ていきましょう。
収益のシミュレーションをしておく
資産運用スタート時の投資額や想定される金利、毎月の投資額などのプランニングも、資産運用の大切な要素です。しっかりとした計画がないまま進めるのではなく、収益についてのシミュレーションを重ねながら、計画性をもって投資を始めましょう。
「どのくらいの収益を得たいのか」「資産運用にどのくらいの期間をかけるのか」なども重要なポイントです。実践したい方法に適した運用期間を把握し、自分の希望通り進められるかシミュレーションしましょう。
長期運用なら投資信託や不動産、短期なら株式投資やFXなど、目的や運用期間、リスクを考慮して投資商品を選ぶことが大切です。目の前の利益だけではなく、長期的な視点を持って運用を進めていくよう常に意識しておきましょう。
本などを読んで勉強しておく
投資に関する知識が全くない状態で資産運用を始めるのは厳しいです。専門書や経済紙などを読んで勉強し、ある程度必要な知識を身につけてから始めましょう。
信頼できる専門家に相談したり、資産運用に関するセミナーに参加したりすることで、独学では得られない情報を得ることもできます。
投資家が集まるサロンやネイチャーグループなどを積極的に利用して、投資家としての見識を広めることをおすすめします。
長期で複利のメリットを活かす
元本のみが利息の対象となる単利と違い、元本に上乗せされた金利にも、次回以降の金利がかかるのが複利です。投資を成功させるためには複利の効果を利用し、長期の運用で元本も増やしていくのがよいでしょう。
複利のメリットを活かすと、最終的には数十万円の差が出る可能性もあり、資産を大幅に増やすことが期待できます。
少額で始める
資産運用は少額から始めることをおすすめします。最初から多額の資金を投資し、万が一損失が発生した場合、金銭的・精神的負担が大きくなってしまうからです。
少額投資であれば、失敗したとしても焦らずに対処でき、経験としてその後のノウハウに役立てることもできます。まずは経験を積むことを重視し、慣れてきたら投資額を徐々に増やし、自身で投資額をコントロールしながら資産運用を続けていきましょう。
なお、「【令和3年最新】初心者におすすめの資産運用ランキング5選|少額から始めてみよう! 」では、初心者におすすめの資産運用をランキング形式でご紹介しています。資産運用で失敗したくない初心者の方は、ぜひご覧ください。
初心者におすすめの資産運用ランキング9選
ここからは、初心者におすすめの運用方法ランキング9選をご紹介します。これから資産運用を始める人はぜひチェックしてください。
- 株式投資
- 不動産投資
- 投資信託
- iDeco(個人型確定拠出年金)
- REIT(不動産投資信託)
- 個人向け国債
- ソーシャルレンディング
- つみたてNISA/NISA
- ロボアドバイザー
それぞれの項目について詳しく見ていきましょう。
①株式投資|株主優待がお得
株式投資は、企業が発行する株を購入し、配当金や値上がり益などを受け取る方法です。主流な資産運用のひとつであり、投資というと株を思い浮かべる人も多いでしょう。
投資初心者には、どの株式を購入すべきか判断するのが難しいかもしれません。そこで、日常生活でよく目にする商品や、話題のサービスに注目してみましょう。中には、株主優待として自社商品や関連サービスを提供している企業もあります。好きな企業や応援したいと思えるブランドの株式を選ぶことで、投資へのモチベーションも高まるでしょう。
ただ、株価は値下がりするリスクも十分にありえます。株式投資で損をしないためには、最低限の業界研究や企業分析が必要でしょう。
LINE証券はスマホアプリに特化したネット証券サービスで、国内株式を1株から購入できる手軽さが魅力です。低価格帯の銘柄も多数扱っていることに加え、チャートがシンプルでわかりやすいので、ぜひ下記からLINE証券に申し込んでみてください。
②不動産投資|自己資金が多いなら検討する価値あり
不動産投資は、土地や建物を購入して、家賃収入や売買による利益を得る投資方法です。賃貸の場合、年単位などの契約が一般的なため、長期的に一定の収入が見込めます。短期間での値崩れや変動も少ない点も特徴です。
ただ、他の資金運用方法に比べてイニシャルコストは高額で、不動産の維持費用が発生するという点には注意が必要です。また、初期投資額を収入が上回るまで赤字が続き、居住者がいないと収入はありません。
ローンを利用するという手段もありますが、不動産知識がない初心者にとってはリスクです。数千万円単位の資金が手元にある人が、資産運用方法を検討する際の選択肢といえます。
JPリターンズは、不動産初心者が確かな知識を持って投資に進むことをサポートするため、投資セミナーを実施しています。1部をマンション投資セミナー、2部を個別の質疑応答・相談にあてており、内容も非常に充実。スムーズな投資への理解を助けているので、ぜひ下記からJPリターンズの不動産投資セミナーに申し込んでみてください。
③投資信託|専門知識がなくても始められる

投資信託は、複数の投資家から調達した資金を、運用のプロであるファンドマネージャーに任せる方法です。国内外の株式や債券、不動産などへ ファンドマネージャーが分散投資し、運用収益が投資家へ還元されます。専門的な知識や経験が少なくても少額から運用を始められるでしょう。
運用方法によって主に次の4タイプに分けられます。
- インデックス型
- アクティブ型
- バランス型
- レバレッジ型
中でもバランス型は、分散投資によってリスクを抑えることができます。また、インデックス型は、特定の指数の値動きと投資信託の基準価額が連動するように設計されており、初心者でもわかりやすいためおすすめの投資方法です。
なお、「【2021年最新】投資信託のおすすめ人気ランキング5選 | メリット・デメリットも解説 」では、インデックス型やアクティブ型をはじめ、おすすめの投資信託銘柄などを詳しく解説しています。投資信託の具体的な知識を得たい方は、併せてお読みください。
④iDeCo(個人型確定拠出年金)|節税したい人におすすめ
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、私的年金制度です。自分で自由に設定した金額を積み立てし、60歳を過ぎてから受け取ります。積み立てた掛金は全額所得控除され、運用益も非課税、受け取る給付金も控除対象である点が最大のメリットです。元本割れのリスクがないため、初心者でも安心して始められるでしょう。
ただ、iDeCoの申し込みから掛け金の設定、運用方法の選定までは自分で行わなければなりません。また、iDeCo加入中には毎月一定の手数料の負担が生じます。一旦掛け金として預けたお金は、原則60歳まで引き出せない点にも注意しましょう。
⑤REIT(不動産投資信託)|自己資金は少ないけれど不動産投資を始めたい人向け
REIT(不動産投資信託)は、オフィスビルや商業施設などの不動産限定で資産運用する投資信託です。賃貸収入や売買を通して出た利益が投資家に分配されます。
運用自体はプロに任せることができるため、初心者でも始めやすいでしょう。また、REITは投資法人が取り扱っており、分配金が比較的高い点も魅力です。
一般的な不動産投資には、数千万円単位の高額な初期費用が必要ですが、REITなら数十万円からスタート可能。不動産投資に興味があって、金額がネックだと感じている人にもおすすめです。ただ、自然災害や投資法人の倒産といったリスクにより、相場や価格の変動が起きる可能性があります。
⑥個人向け国債|安定性重視の人にはぴったり

個人向け国債は、国が資金調達目的で発行している債券の「国債」のうち、個人が購入できるものです。個人向け国債には次の3つの種類があり、それぞれ金利の種類や設定が異なります。
- 3年間固定
- 5年間固定
- 10年変動
通常の国債は一度投資すると基本的に解約できませんが、個人向けの場合は1年経つと途中解約が可能です。また、1万円前後の少額から始められるので、リスクを極力抑えて投資を始めたい初心者に適しています。
元本割れの心配はありませんが、金利は比較的低めなので大きなリターンは期待できないでしょう。他の投資方法と組み合わせて分散投資すると効率的です。
⑦ソーシャルレンディング|利回りが高く貸し倒れが少ない注目の投資方法
ソーシャルレンディングとは、個人の投資家と企業のを仲介するオンライン上のマッチングサービスで、クラウドファンディングの一種です。利回りは約5〜7%と比較的高い上、貸し倒れが少なく、有効な資産運用手段として近年注目を集めています。
1万円前後の少額から参加できる商品もあり、オンライン上で完結できるため、初心者にも負担が少ないでしょう。ただ、利用する際には、事業主が健全な運営を行っているか、貸し倒れの可能性がないかをよくチェックする必要があります。
また、2年や3年といった長期案件は、市場の変化などによるリスクも考慮しましょう。日本におけるソーシャルレンディングはまだ発展途上の段階であり、今後の動向に注目が集まっています。
⑧つみたてNISA/NISA|株式投資・投資信託を始めるならぜひ取り入れたい
NISA(ニーサ)は、少額投資非課税制度とも呼ばれ、株式投資や投資信託の配当金や売却益が非課税となる制度です。NISAには次の3つの種類があります。
| NISAの種類 | 非課税対象の上限額 | 投資可能期間 |
| 一般NISA | 年120万円 | 2014年〜2023年 |
| つみたてNISA | 年40万円 | 2018年〜2037年 |
| ジュニアNISA | 年80万円 | 2016年〜2023年 |
注意点としては、NISAの開設は1人1口座まで、NISAの利用は新規投資に限られる点です。また、金融機関は1年毎に変更可能ですが、既にNISAで保有中の資産を移すことはできません。
ちなみに、NISAとiDeCoの併用はできませんが、つみたてNISAとiDeCoの併用は可能です。税金対策をしながら将来的な資金を貯めていきたい人は、ぜひ利用しましょう。
積立投資(年間20万円まで)と株式投資・投資信託(年間102万円まで)がセットになった「新NISA」も2024年以降に新設予定です。
⑨ロボアドバイザー|忙しい人や投資初心者におすすめ
ロボアドバイザーは、人工知能(AI)が投資商品の選定や発注を行うサービスです。投資家は開始時に、どのくらいまでリスクを取るか、資産運用の目的などの項目に答えるだけ。
最適な商品の組み合わせやポートフォリオの提案、実際の投資などの対応を本人に代わって自動的に行ってくれます。投資の専門的な知識不要で始められるため、初心者に最適です。投資信託のように人間に任せるサービスよりも手数料は安く済みます。
ただし、ロボアドバイザーに従って投資しても、元本割れの可能性はある点は理解しておいてください。過信することなく、サポートとして使いながら、自分でも勉強していくことをおすすめします。
なお、「【令和3年最新】初心者におすすめの資産運用ランキング5選|少額から始めてみよう!」では、資産運用が初めてでも安心して実践できる運用方法を紹介しています。詳しく知りたい方は、ぜひご覧ください。
1000万円でできるおすすめの資産運用5選
手元に1000万円の余剰資金があったら、資金運用にどのような選択肢があるのでしょうか。1000万円でスタートできるおすすめの資産運用は、以下の5つです。
- 定期預金
- 保険
- 仮想通貨
- ヘッジファンド
- 不動産私募ファンド
それぞれの特徴やメリットとデメリットを紹介していきますので、どの方法がよいかを見極める際に役立ててください。
定期預金|1,000万円まで元本保証。リターンはほぼない
定期預金は、ローリスクの資産運用です。決められた期間銀行に預金することで、普通預金よりも高い金利が適用されます。銀行預金は1000万円までペイオフ(預金保護)が適用され、万が一銀行が潰れてしまっても元本は保証されます。
一方、300~1000万円未満で1年間の定期預金の年利相場は、一般的な都市銀行・地方銀行の年利が0.01%、ネット銀行でも年0.02~0.05%と非常に低いです。
年利0.02%のネットバンクに1年の間、1,000万円を預けた場合、利息は2,000円です。そこから約20%の税金が差し引かれます。利益はほとんど出ないので、定期預金では資産を増やすのではなく、資産を守るものという認識で運用することをおすすめします。
| メリット | ・元本割れの心配がない ・銀行口座を開設すればいつでも始められる |
| デメリット | ・金利が非常に低い ・原則満期まで自由に引き出せない |
保険|投資と保障を兼ね備えた手堅い投資方法
保険には、保障の他に貯蓄の機能がついた貯蓄型保険があります。貯蓄型保険の種類は以下の通りです。
- 養老保険
- 学資保険
- 終身保険
貯蓄型の保険は、一定の期間保険料を支払い続けることで、満期時に収めた保険料以上のお金が戻ってくるため、自分で運用する必要はありません。しかし、満期前に解約すると、元本割れが起こる可能性があるため注意が必要です。
貯蓄型保険は、死亡時の保障として活用しつつ資産運用ができます。長期的に手堅く資産運用をしたいという方に向いている資産運用です。
| メリット | ・定期預金よりも高利率で手続きが簡単 ・病気や怪我をしたときに保証がおりる |
| デメリット | ・満期前に解約すると元本割れの可能性がある ・加入期間が長く流動性が悪い |
仮想通貨|大きな利益を得られる可能性があるがタイミングが重要

仮想通貨とは、実際には存在しない電子通貨をインターネット上でシステム化し、売買することで利益を得る方法です。ビットコインやイーサリアム、リップルといった種類があります。
利回りは投資のタイミングによって異なり、月利+10%以上になることもあります。短期的に大きな収益を得られる「仮想通貨FX」のようなシステムを導入している会社もあり、24時間365日取引が可能です。
| メリット | ・少額で始められ、さまざまな仮想通貨に分散投資が可能 ・24時間365日取引可能 |
| デメリット | ・仮想通貨市場自体がまだ発展途上であるため不安定で信用性に欠ける ・他の投資方法に比べて税率が高い |
ヘッジファンド|プロに運用を代行してもらえる。高額な自己資金が必要
ヘッジファンドとは、投資のプロに資金を預けて運用を代行してもらう運用方法です。投資信託では投資家が自由に商品を選べますが、ヘッジファンドでは制限が設けられているという違いがあります。
ヘッジファンドの魅力は高い利回りにあり、期待利回りは10%ほどで、他の金融商品とはかなりの差です。年利10%で1,000万円を複利運用した場合、期待利益は1年で約100万円、5年で約610万円、10年では約1,593万円となり、ハイリターンが期待できます。
最低投資額の1,000万円が用意できるなら、投資信託よりも高いリターンを得られる投資方法です。
| メリット | ・プロに任せることで失敗しにくい ・高い利回りで大きなリターンが期待できる |
| デメリット | ・最低投資額が1,000万円と高額 ・元本割れのリスクがある |
不動産私募ファンド|初期費用と専門知識が必要だが利回りが高い
投資家から資金を募って運用する事業のなかで、資金を募る対象者を狭く限定しているものを私募ファンドといいます。
不特定多数の投資家が希望の不動産物件に投資できるREITとは違い、特定の投資家に限定して募集を行うのが「不動産私募ファンド」です。一般的に、ハイリスク・ハイリターンの運用をめざすことが多く、投資初心者には難易度が高い投資方法といえます。
| メリット | ・REITに比べて高いリターンが期待できる ・運用の自由度が高め |
| デメリット | ・多額の初期費用が必要 ・専門的な知識が求められる |
おすすめ人気ネット証券会社9選

おすすめの人気ネット証券を9つ紹介します。数百円からでも株を購入できる少額の株式投資サービスなど、初心者でも使いやすいよう配慮されたものも多数ありますので、ぜひチェックしてください。
1つずつ詳しく紹介していきます。
※詳細情報は2021年6月10日時点のものです。
SBI証券|約定金額100万円以下なら手数料無料

全国120店舗以上を展開する大手証券会社によるSBI証券は、口座開設数とシェア数で業界トップクラスの人気を誇ります。取引手数料が安く、約定金額100万円以下は手数料は無料です。
他にも、取り扱っている商品の豊富さやツールの充実度など魅力が満載。投資を続ける上で必要なサービスがバランスよく盛り込まれています。ベテランからも支持されており、初心者も無理なく投資を始めることができるでしょう。
| 最低購入単位 | 1株 |
| 売買手数料 | 0.1~1.0% |
| おすすめポイント | ・100万円までの国内株式の取引手数料無料 ・IPO取扱い銘柄数が業界でもトップクラス ・Tポイント投資が可能 |
| キャンペーン | ・SBI証券の総合口座開設とSBIハイブリッド預金への入金でSBIハイブリッド預金の受取利息100倍 ・クイズに正解&フォロー&リツイートでAmazonギフト券200円プレゼント |
松井証券|毎月現金が戻ってくる!投信キャッシュバックサービスが魅力
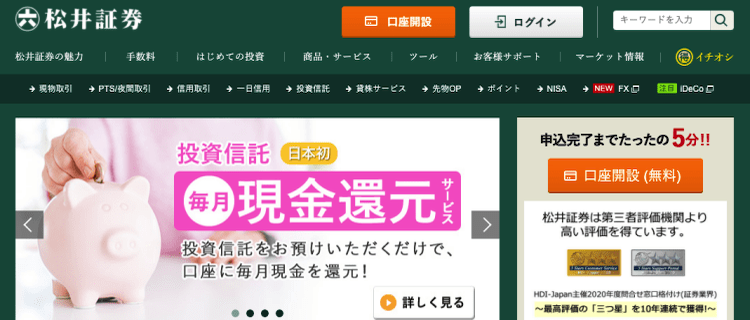
松井証券は、創業100年以上という老舗の大手証券会社が運営しています。1日の約定金額が50万円までは手数料無料で利用可能、それ以降の手数料もシンプルな体系です。
国内の証券会社では唯一とされる「投信キャッシュバックサービス」を実施しています。返済期限が1日限りの1日信用取引は、デイトレーダーからも人気です。少額からリスクを抑えて投資を始めたい人におすすめです。
| 最低購入単位 | 1株 |
| 売買手数料 | 0.2~1.0% |
| おすすめポイント | ・1日の売買金額50万円以下は手数料無料 ・長い歴史を持つ老舗証券会社で信頼性が高い ・信託報酬の一部が現金還元される制度によりお得に資産運用できる |
| キャンペーン | ・新規口座開設+投資信託への積立が合計6,000円以上でもれなく現金1,000円プレゼント ・口座開設で全員に200ポイントプレゼント |
楽天証券|楽天ポイントで投資ができる
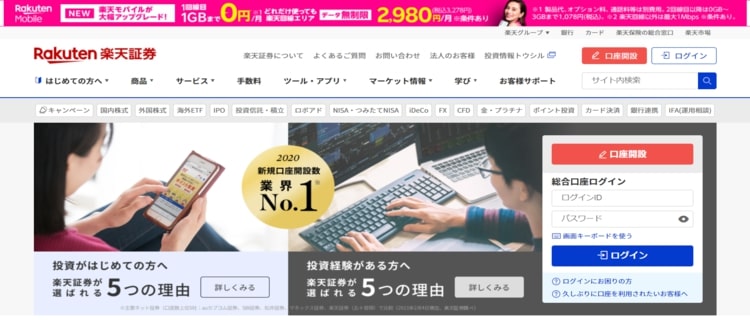
楽天証券は、機能性やサービスが充実したネット証券です。楽天ポイントを使って投資ができる上、取引手数料や投信の保有残高などに応じたポイントも付くため効率よく運用ができます。
株アプリのiSPEED(アイスピード)は、3タップでスマホから注文できる、初心者にも優しい設計となっています。口座開設もスピーディで、楽天銀行との連携により入出金も簡単です。
| 最低購入単位 | 1株 |
| 売買手数料 | 0.3~1.0% |
| おすすめポイント | ・投資しながら楽天ポイントが貯まるポイントプログラム ・楽天会員は個人情報入力不要でスピード口座開設 ・スマホやパソコン対応の取引ツールで快適 |
| キャンペーン | ・口座開設から最大3ヶ月間現物取引手数料全額キャッシュバック ・楽天カード新規入会&投信積立楽天カード決済で入会特典+1,000ポイントプレゼント |
LINE証券|有名会社1,000銘柄を1株単位で買える

LINE証券は、スマホ投資専門のネット証券です。1株単位で買える国内の有名会社1,000銘柄を「いちかぶ(単元未満株)」で取引可能。自己資金0円から投資を始められます。
スマホに特化した見やすい画面で、初心者でも簡単に操作を覚えられるでしょう。いつものLINEアプリからサクサク操作できておすすめです。
| 最低購入単位 | 1株 |
| 売買手数料 | 0.2~1.0% |
| おすすめポイント | ・取引手数料が業界最安レベル ・LINEアプリを通して取引可能 ・LINE Payでの入金可能でLINEポイントでの投資もできる |
| キャンペーン | ・口座開設してクイズに答えると最高3株分の購入代金プレゼント ・キャンペーンに参加で最大4000円相当キャッシュバック |
マネックス証券|IPO株購入のチャンスあり

マネックス証券は、大手ネット証券のひとつです。自動売買機能の他、トレードに役立つさまざまなツールが用意されています。手数料も良心的なので、初心者も始めやすいでしょう。投資信託など運用を通じてマネックスポイントが貯まる点も魅力です。
IPO株は完全抽選方式で購入できるため、誰にでも平等に当選チャンスがあります。米国株の取り扱い数が多く、アメリカの株式に興味がある人にもおすすめです。
| 最低購入単位 | 1株 |
| 売買手数料 | 1.1% |
| おすすめポイント | ・IPO株は抽選で平等に決まる ・NISA残高にも年率0.03%のポイント付与 ・プロのアナリストによる分析や著名投資家のポートフォリオ解析サービスも |
| キャンペーン | ・投資信託の抽選対象金額30万円以上で抽選でマネックスポイント10,000ポイント ・新規口座開設等でAmazonギフト券200円プレゼント |
DMM株|米国株に投資するならおすすめ

オンライン業界の大手企業であるDMMが運営するDMM株。約定ごとの金額が5万円以下の場合は手数料は55円と良心的です。また、米国株は売買金額に関わらず手数料無料で取引できます。
最短翌日の口座開設が可能なため、スピーディに投資をスタートできる点も魅力です。表示の切り替えもできるツールは、直感的な操作で初心者でも使いやすいでしょう。
| 最低購入単位 | 1株 |
| 売買手数料 | 0.02~0.8% |
| おすすめポイント | ・最短翌日から取引できるスピード口座開設 ・手数料が良心的 ・米国株式の取引手数料は無料 |
| キャンペーン | ・新規口座開設・登録完了で国内株式が1ヶ月間取引手数料無料 ・新規口座開設で抽選で2,000円キャッシュバック |
岡三オンライン証券|取引ツールが見やすくて優秀

岡三オンライン証券は、創業95年以上という老舗の証券会社が運営するネット証券です。近年、口座開設数が急増しており、注目を集めています。上場投信以外の投資信託では購入手数料が無料、他の取引の手数料も良心的な設定です。
シンプルな表示ながら、必要な機能はしっかり備えた取引ツールも好評。初心者からベテランまで幅広い層におすすめします。
| 最低購入単位 | 1株 |
| 売買手数料 | 0.5~1.0% |
| おすすめポイント | ・上場投信以外の投資信託の購入手数料なし ・取引ツールや機能が充実 ・老舗証券会社ならではの安心感 |
| キャンペーン | ー |
SMBC日興証券|信用取引の委託手数料が無料でコストを抑えられる

SMBC日興証券は、大手証券会社による人気ネット証券で、信用取引の委託手数料が無料な点が大きな特徴です。日興フロッギーというウェブサービスを使えば、記事から直接株を購入できます。
分析レポートが豊富で、AI株式ポートフォリオ診断などユニークなツールも無料で利用可能。高機能ロボアドバイザーによる銘柄アドバイスも利用できるなど、初心者にもありがたいツールが充実しています。
| 最低購入単位 | 1株 |
| 売買手数料 | 0.07〜0.1% |
| おすすめポイント | ・日興フロッギーの記事から株式購入ができる ・dポイントでの投資も可能 ・ANAマイレージクラブ会員なら新規口座開設で200マイル付与 |
| キャンペーン | ・個人向け国債購入で対象金額に応じて現金プレゼント ・国内現物株式の取引で委託手数料200円(税込)ごとdポイント進呈 |
GMOクリック証券|初心者でも使いやすいスマホアプリがある

GMOクリック証券は、売買手数料の安さが好評で、NISA口座では手数料が無料です。高機能ながら直感的に操作できるスマホアプリは、初心者でも使いやすいでしょう。
GMOあおぞらネット銀行の口座連携サービスを使うと、優遇金利やスピーディな資金移動などのメリットを受けられます。取引ツールや投資情報分析ツールも充実しており、注目を集めるネット証券のひとつです。
| 最低購入単位 | 1株 |
| 売買手数料 | 0.3~1.0% |
| おすすめポイント | ・業界トップクラスの格安手数料体系 ・直感的な操作が可能なスマホアプリ ・株主優待利用で株の売買手数料キャッシュバック |
| キャンペーン | ・新規FX口座開設+取引で最大30,000円キャッシュバック |
なお、「【2021年最新】ネット証券のおすすめ人気ランキング11選|証券会社を選ぶポイントは?」では、おすすめのネット証券をランキング形式でご紹介しています。また、「ネット証券の口座開設までの流れとは?必要書類や日数も徹底解説!」ではネット証券で口座を開設する流れを紹介しています。ネット証券で資産運用を検討中の方は、ぜひご覧ください。
まとめ:資産運用はリスクが少ない方法で少額から始めよう
資産運用には多くの種類があり、それぞれの特徴やメリット・デメリットがあります。
プロに運用を任せる投資信託や自分の知識や才覚が求められるFXなど、投資家に必要な知識もさまざまです。
事前のリサーチとシミュレーションを行い、できる限りリスクを回避して資産を運用しましょう。経験がない初心者の方は、最初から大きなリターンを狙うのではなく、リスクが少ない方法で、少額から始めてみてはいかがでしょうか。
少額での株式投資におすすめな証券会社TOP3です。今ならお得なキャンペーンもやっているため、すぐに無料登録しましょう。
少額株式投資におすすめな証券会社
- 楽天証券|取引コストが低く、取引ツールが使いやすい
- PayPay証券|1000円で世界的企業の株主になれる
- SBIネオモバイル証券 ネオモバ|Tポイントを使って株式投資ができる